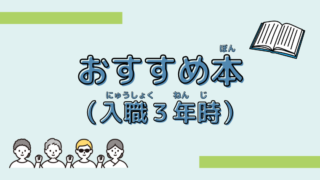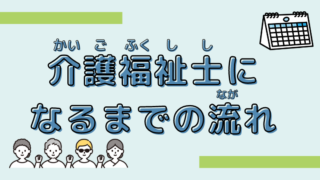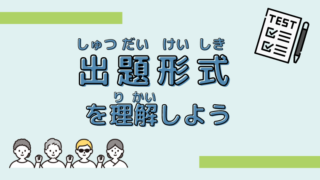科目別過去問|10.コミュニケーション技術

どんな問題が出る?
ここでは、「人間関係とコミュニケーション」の科目と異なり、実際に現場で必要となるコミュニケーションの方法論について出題されます。
第35回試験から問題数は、6問に減りました。
利用者の特性に応じたコミュニケーション方法が問われるので、障害や疾病、家族への対応など様々な知識が求められます。
事例を読んで答える問題もあるため、事例の中から何を求められているのか読み解く必要もあります。
各障害、疾病別の特徴やその対応をおさえておけば、現場での仕事に近い範囲ですので、難易度は高くはありません。
しっかりと点数を積み上げたい科目です。
「人間関係とコミュニケーション」とあわせて、最低1点をとる必要があります。
過去問挑戦
第37回(2025年)
次の記述のうち,利用者とのコミュニケーションの場面で用いる要約の技法として,適切なものを1つ選びなさい。
次の記述のうち,利用者と家族の意向が異なるとき,家族とのコミュニケーションにおいて介護福祉職が留意すべき点として,適切なものを1つ選びなさい。
Aさん(80歳,男性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所している。アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)が進行している。ある日の昼食時,介護福祉職がAさんに配膳すると,「お金はこれしかありません。足りますか」と小さくたたまれたティッシュペーパーを渡してきた。
このときのAさんに対する介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
構音障害のあるBさんは,現在発語訓練を実施中である。ある日,介護福祉職に対して,「おあんで,あつがおごれた」と訴えた。介護福祉職は,Bさんの発語をうまく聞き取れず,「もう一度,言ってください」と伝えた。Bさんは,自身の発語で会話を続けようとしているが,介護福祉職には,その内容を十分に理解することができなかった。
このときの,Bさんに対する介護福祉職の判断として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Cさん(55歳,男性)は,知的障害がある。3か月前に,施設から居宅での一人暮らしに移行し,現在は,居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら生活している。ある日,Cさんが,「ゴミ,分けて捨てるの,難しいよ」と言うので,室内に分別収集の説明書を貼って,カレンダーに収集日を書くことにした。そして,介護福祉職は,「この説明書とカレンダーを見て,捨てるといいですよ」とCさんに伝えた。その後,Cさんは努力していたが,分別できなかったゴミが少しずつ増えていった。
次のうち,Cさんにかける介護福祉職の最初の言葉として,最も適切なものを1つ選びなさい。
介護保険サービスにおける記録に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
第36回(2024年)
Cさん(85歳,女性,要介護3 )は,介護老人保健施設に入所しており,軽度の難聴がある。数日前から,職員は感染症対策として日常的にマスクを着用して勤務することになった。
ある日,D介護福祉職がCさんの居室を訪問すると,「孫が絵を描いて送ってくれたの」と笑いながら絵を見せてくれた。D介護福祉職はCさんの言動に共感的理解を示すために,意図的に非言語コミュニケーションを用いて対応した。
このときのD介護福祉職のCさんへの対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
利用者の家族との信頼関係の構築を目的としたコミュニケーションとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
Eさん(70歳,女性)は,脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で言語に障害がある。発語はできるが,話したいことをうまく言葉に言い表せない。聴覚機能に問題はなく,日常会話で使用する単語はだいたい理解できるが,単語がつながる文章になるとうまく理解できない。ある日,Eさんに介護福祉職が,「お風呂は,今日ではなくあしたですよ」と伝えると,Eさんはしばらく黙って考え,理解できない様子だった。
このとき,Eさんへの介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Fさん(70歳,女性)は,最近,抑うつ状態(depressive state)にあり,ベッドに寝ていることが多く,「もう死んでしまいたい」とつぶやいていた。
Fさんの発言に対する,介護福祉職の言葉かけとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
Gさん(70歳,女性,要介護1)は,有料老人ホームに入居していて,網膜色素変性症(retinitis pigmentosa)による夜盲がある。ある日の夕方,Gさんがうす暗い廊下を歩いているのをH介護福祉職が発見し,「Hです。大丈夫ですか」と声をかけた。Gさんは,「びっくりした。見えにくくて,わからなかった…」と暗い表情で返事をした。
このときのGさんに対するH介護福祉職の受容的な対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
事例検討の目的に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
第35回(2023年)
次のうち,閉じられた質問として,適切なものを1つ選びなさい。
利用者の家族と信頼関係を形成するための留意点として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Cさん(75歳,男性)は,老人性難聴(presbycusis)があり,右耳は中等度難聴,左耳は高度難聴である。耳かけ型補聴器を両耳で使用して静かな場所で話せば,なんとか相手の話を聞き取ることができる。
Cさんとの1対1のコミュニケーションの方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Dさん(90歳,女性,要介護5)は,重度のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimerʼs type)である。介護福祉職は,Dさんに声かけをして会話をしているが,最近,自発的な発語が少なくなり,会話中に視線が合わないことも増えてきたことが気になっている。
Dさんとのコミュニケーションをとるための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
介護実践の場で行われる,勤務交代時の申し送りの目的に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
Eさん(87歳,女性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所していて,認知症(dementia)がある。ある日,担当のF介護福祉職がEさんの居室を訪問すると,Eさんは,イライラした様子で,「私の財布が盗まれた」と言ってベッドの周りをうろうろしていた。一緒に探すと,タンスの引き出しの奥から財布が見つかった。
F介護福祉職は,Eさんのケアカンファレンス(care conference)に出席して,この出来事について情報共有することにした。
Eさんの状況に関する報告として,最も適切なものを1つ選びなさい。
第34回(2022年)
介護福祉職が利用者とコミュニケーションをとるときの基本的な態度として,最も適切なものを1つ選びなさい。
介護福祉職によるアサーティブ・コミュニケーション(assertive communication)として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Jさんの発言への介護福祉職の共感的理解を示す対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
Jさんの不安な気持ちを軽くするための介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
訪問介護員(ホームヘルパー)が,興奮しているときのKさんとコミュニケーションをとるための方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
長男に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
利用者の家族から苦情があったときの上司への報告に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
利用者の自宅で行うケアカンファレンス(care conference)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。