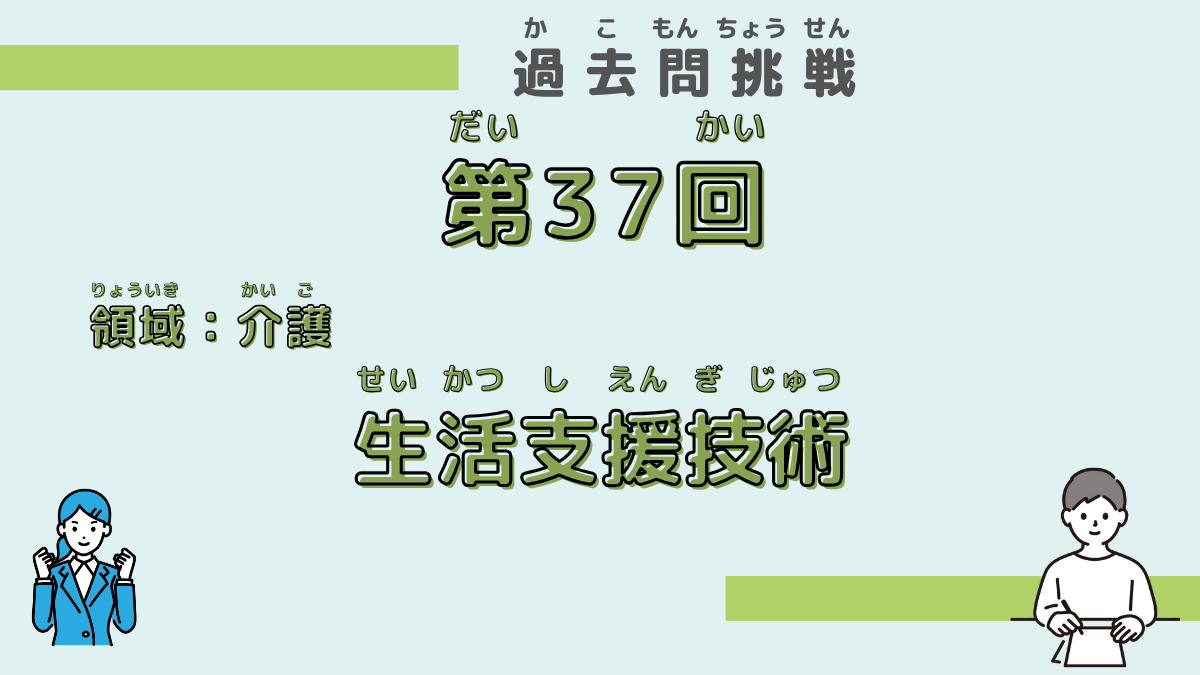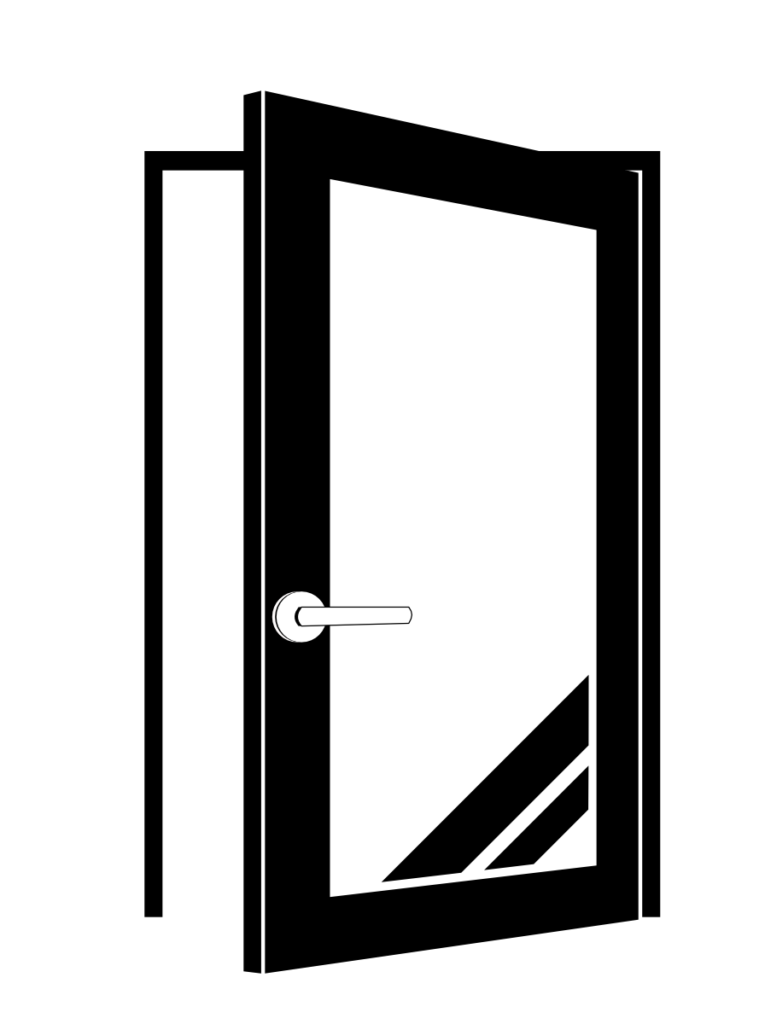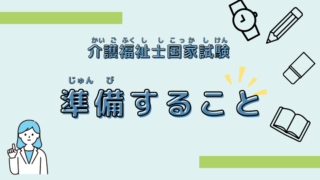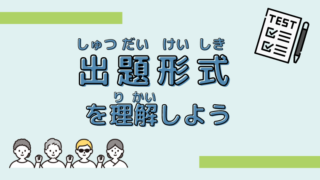生活支援技術
問題88
次の記述のうち,口腔ケアを実施するときの留意点として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 実施中は,利用者に顎を上げた姿勢をとってもらう。
2 総義歯は,上顎から下顎の順に外してもらう。
3 歯みがきの前に,うがいを行ってもらう。
4 歯ブラシは,大きく動かして磨いてもらう。
5 舌ブラシは,舌先から咽頭に向かって動かしてもらう。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題88(解答と解説)
口腔ケアを実施するときの留意点に関する問題です。
答えは、「3」です。
口腔ケアは、口の中を清潔に保ち、誤嚥性肺炎などの感染予防に役立ちます。
安全で効果的に行うための姿勢や手順、道具の使い方など、実施時の留意点を理解することが重要です。
1 実施中は,利用者に顎を上げた姿勢をとってもらう。
【×】誤りです。顎を上げすぎると誤嚥の危険が高まります。口腔ケアを行う際は、軽くうつむいた姿勢を保ち、誤嚥を防ぐことが大切です。
2 総義歯は,上顎から下顎の順に外してもらう。
【×】誤りです。総義歯は,下顎から外します。
3 歯みがきの前に,うがいを行ってもらう。
【○】正しい選択肢です。うがいを先にすることで、口の中の食べかすや汚れをあらかじめ取り除き、歯みがきの効果を高めることができます。
4 歯ブラシは,大きく動かして磨いてもらう。
【×】誤りです。歯ブラシは小刻みに優しく動かして磨くのが基本です。
5 舌ブラシは,舌先から咽頭に向かって動かしてもらう。
【×】誤りです。舌ブラシは、奥(咽頭側)から舌先に向かってやさしく動かします。
問題89
次の記述のうち,介護が必要な人への熱中症対策のために,介護福祉職が行う水分補給の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 のどが渇いてから,水分を取るように伝える。
2 水でむせるときは,ゼリーの提供を控える。
3 起床時は,水分摂取を控えるように伝える。
4 食事のときの水分は,一日の水分摂取量から除く。
5 汗の量が多いときは,塩分を含んだ飲み物を勧める。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題89(解答と解説)
熱中症対策に関する問題です。
答えは、「5」です。
高齢者や介護が必要な人は、のどの渇きを感じにくく、脱水や熱中症になりやすいため、日常の水分補給の支援が重要です。
今回の問題では、体の状態にあわせた適切な水分補給の対応が問われています。
1 のどが渇いてから,水分を取るように伝える。
【×】誤りです。高齢者は、のどの渇きを感じにくいことがあります。のどが渇いてからでの対応では遅い場合があるため、渇く前にこまめに水分を取るようにします。
2 水でむせるときは,ゼリーの提供を控える。
【×】誤りです。水でむせるときは,トロミをつけたゼリー飲料のほうが安全に飲めます。
3 起床時は,水分摂取を控えるように伝える。
【×】誤りです。寝ている間に汗をかいているため、起床時の水分補給はとても大切です。
4 食事のときの水分は,一日の水分摂取量から除く。
【×】誤りです。汁物や飲み物など、食事中に取る水分も一日の水分摂取量に含まれます。
5 汗の量が多いときは,塩分を含んだ飲み物を勧める。
【○】正しい選択肢です。汗をかくとは、水分と一緒に塩分(電解質)も失われるため、経口補水液やスポーツドリンクなどの塩分を含む飲み物が有効です。
問題90
Aさん(75歳,男性)は, 1年前に前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断され,現在は,認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居している。若い頃から食べることが好きである。現在,咀嚼や嚥下機能の低下はなく,スプーンを使い,自分で食べている。最近,飲み込む前に次々と食べ物を口に入れることが増えた。
次の記述のうち,Aさんの現在の状態に合わせた食事の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 取っ手つきのコップを準備する。
2 食器に少量ずつ盛りつけて提供する。
3 すべての料理をテーブルの上に並べる。
4 大きなスプーンに変更する。
5 手で持って食べられる物を準備する。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題90(解答と解説)
食事の介護に関する問題です。
答えは、「2」です。
前頭側頭型認知症の特徴として「衝動の抑制がききにくくなる」ことがあります。
今回の事例のポイントは次の部分です。
飲み込む前に次々と食べ物を口に入れるという課題に対する、安全面に配慮した環境調整や提供方法の工夫が必要となります。
1 取っ手つきのコップを準備する。
【×】誤りです。コップの形状は、飲みやすさのサポートにはなりますが、Aさんの課題の改善にはなりません。
2 食器に少量ずつ盛りつけて提供する。
【○】正しい選択肢です。視覚的にたくさんの食べ物があると、衝動的に次々と口に入れてしまうことがあります。 少量ずつ盛り付けることで、一度に食べ過ぎないようにします。
3 すべての料理をテーブルの上に並べる。
【×】誤りです。視覚的にたくさんの食べ物があると、衝動的に次々と口に入れてしまうため、逆効果です。
4 大きなスプーンに変更する。
【×】誤りです。スプーンが大きくなると、一口の量が増えてむせや誤嚥のリスクが高くなります。 飲み込む前に次々と口に入れてしまうAさんのような人には向きません。
5 手で持って食べられる物を準備する。
【×】誤りです。Aさんはスプーンを使って食べることはできています。今回の課題の改善には直接関係がありません。
#前頭側頭型認知症
問題91
次の記述のうち,パーキンソン病(Parkinson disease)で上肢の震えはあるが,自力摂取が可能な利用者の食事の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 食事後に口腔内のアイスマッサージを行う。
2 片側の縁が高くなっている皿を準備する。
3 上半身を後ろに20度程度倒すように伝える。
4 食器の置いてある位置を説明する。
5 踵を床から浮かすように伝える。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題91(解答と解説)
食事の介護に関する問題です。
答えは、「2」です。
パーキンソン病は、手足のふるえ(振戦)や動きが遅い(動作緩慢)、筋肉のこわばり(筋固縮)が特徴です。
この問題では、自力で食事ができる人への食事動作を助ける環境調整や道具の工夫が問われています。
1 食事後に口腔内のアイスマッサージを行う。
【×】誤りです。アイスマッサージは、嚥下障害(飲み込みにくさ)がある場合に効果がありますが、上肢の震えの課題解決にはなりません。
2 片側の縁が高くなっている皿を準備する。
【○】正しい選択肢です。上肢が震えていても、自分で食べられるようにするために、皿の縁を高くして食べ物をすくいやすくする工夫はとても有効です。
3 上半身を後ろに20度程度倒すように伝える。
【×】誤りです。食事中に上体を後ろに倒すと、誤嚥のリスクが高まり危険です。
4 食器の置いてある位置を説明する。
【×】誤りです。視覚障害や失認がある場合には有効ですが、上肢の震えの課題解決にはなりません。
5 踵を床から浮かすように伝える。
【×】誤りです。足をしっかり床につけることで体が安定し、上半身の動作もしやすくなります。 踵を浮かせるのは転倒や姿勢の不安定につながるため不適切です。
問題92
次の記述のうち,入浴の作用を生かした,高齢者への入浴の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 食事は,入浴直前に摂取する。
2 高血圧の人には,42℃以上の湯につかってもらう。
3 浴槽の中では,関節運動を促す。
4 心疾患(heart disease)のある人には,肩まで湯につかってもらう。
5 個浴の浴槽内では,足を浮かせてもらう。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題92(解答と解説)
入浴作用を生かした入浴介護に関する問題です。
答えは、「3」です。
入浴には、身体の清潔保持だけでなく、血行促進やリラックス効果、関節の可動域の向上など様々な作用があります。
特に試験でも問われやすい作用(効果)は、次の3つです。
- 温熱作用(効果)
- 浮力作用(効果)
- 静水圧作用(効果)
1 食事は,入浴直前に摂取する。
【×】誤りです。食事後すぐに入浴をすると、消化不良や貧血を起こすことがあります。食事と入浴の間は、最低でも30分~1時間は空けることが望ましいです。
2 高血圧の人には,42℃以上の湯につかってもらう。
【×】誤りです。42℃以上の熱い湯は、血圧の急上昇や心臓への負担がかかるため、高血圧の人には不適切です。
3 浴槽の中では,関節運動を促す。
【○】正しい選択肢です。浮力作用により、関節の動きが楽になり、痛みも軽減されるため、入浴中の軽い関節運動は高齢者にとって効果的です。
4 心疾患(heart disease)のある人には,肩まで湯につかってもらう。
【×】誤りです。心疾患のある人が肩まで湯につかると、心臓に大きな負担がかかり危険です。 湯量は胸の下あたりまでにし、半身浴などがおすすめです。
5 個浴の浴槽内では,足を浮かせてもらう。
【×】誤りです。浴槽内で足を浮かせると体が不安定になり、転倒や溺れるリスクが高くなります。足裏をしっかり浴槽の底につけるようにし、安定した姿勢を保つことが大切です。
問題93
次の記述のうち,下肢筋力が低下して介護を必要とする人の入浴に適した環境として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 浴室の入口は開き戸にする。
2 床から浴槽の縁までの高さは20cmにする。
3 縦に長く,浅めの洋式の浴槽にする。
4 浴槽の縁の幅は20cmにする。
5 浴槽への出入りのために,水平および垂直の手すりを設置する。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題93(解答と解説)
入浴介護に関する問題です。
答えは、「5」です。
下肢筋力が低下した利用者にとって、安全で負担の少ない入浴環境を整えることは転倒や事故防止のために重要です。
1 浴室の入口は開き戸にする。
【×】誤りです。開き戸(下のイラスト)は、転倒時に外から開けにくくなるため危険です。介護のしやすさや安全性から、引き戸や折れ戸が望ましいとされています。
2 床から浴槽の縁までの高さは20cmにする。
【×】誤りです。一般的に浴槽の縁までの高さは40~45cmが適切とされます。20cmでは低すぎるため、立ち上がりが難しくなります。
3 縦に長く,浅めの洋式の浴槽にする。
【×】誤りです。洋式の浅くて長い浴槽は、体が浮きやすく、立ち上がりが難しくなる場合があります。
4 浴槽の縁の幅は20cmにする。
【×】誤りです。浴槽の縁が広すぎるとまたぐ動作が難しくなり、転倒のリスクが高まります。一般的に10〜15cmが良いとされており、浴槽に腰をかけり、またいだりする際に安定感があるとされています。
5 浴槽への出入りのために,水平および垂直の手すりを設置する。
【○】正しい選択肢です。垂直の手すりは立ち上がりやすく、水平の手すりは移動の安定性を支えます。 両方の手すりを設置することで、安全で自立しやすい入浴環境を整えることができます。
問題94
次の記述のうち,体調不良で入浴できない片麻痺の利用者に対して,ベッド上で行う全身清拭の方法として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 清拭時は,窓を開けて行う。
2 洗面器には,40℃程度のお湯を準備する。
3 最初に,腹部から清拭する。
4 背部は,患側を下にした側臥位にして拭く。
5 蒸しタオルで拭いた後は,乾いたタオルで水分を拭き取る。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題94(解答と解説)
ベッド上で行う全身清拭の方法に関する問題です。
答えは、「5」です。
入浴できない利用者には、感染予防や皮膚の清潔保持のためにも清拭が必要となります。
入浴の場合と寒さの感じ方が異なるため、正しい順序や方法をしっかり覚えましょう。
1 清拭時は,窓を開けて行う。
【×】誤りです。清拭中は利用者の体が冷えやすいため、室温を保つことが大切です。
2 洗面器には,40℃程度のお湯を準備する。
【×】誤りです。清拭の際、タオルを絞ると温度が8〜10℃低下するといわれています。そのため、洗面器には50〜55℃程度のお湯を準備します。
3 最初に,腹部から清拭する。
【×】誤りです。清拭は基本的に心臓に向けて、末梢から中枢に向かって拭いていきます。
4 背部は,患側を下にした側臥位にして拭く。
【×】誤りです。片麻痺の人の場合、麻痺側を下にすると圧迫されて褥瘡の原因になることがあるため、適切ではありません。
5 蒸しタオルで拭いた後は,乾いたタオルで水分を拭き取る。
【○】正しい選択肢です。清拭後に水分が残ると、皮膚のかぶれや冷えの原因になるため、乾いたタオルでやさしく水分を拭き取ることが大切です。
問題95
次のうち,同居の高齢者におむつを使用する家族介護者に対する,介護福祉職の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「使用する本人の羞恥心に気を配りましょう」
2 「尿失禁を防ぐことができます」
3 「尿量を気にせずに, 1日中同じおむつを使うことができます」
4 「おむつを着けると,安心して排泄ができます」
5 「家族の都合に合わせて,おむつを使いましょう」
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題95(解答と解説)
おむつの使用に関する問題です。
答えは、「1」です。
おむつを使用する際には、排泄の自立支援や利用者の尊厳に配慮することが大切です。
介護福祉職だけでなく、家族介護者にもしっかりと理解を求め、適切な使用を助言できるようにします。
1 「使用する本人の羞恥心に気を配りましょう」
【○】正しい選択肢です。おむつの使用は、本人の羞恥心を伴うデリケートなことです。本人の気持ちに寄り添った最大限の配慮が必要です。
2 「尿失禁を防ぐことができます」
【×】誤りです。おむつは尿失禁を「防ぐ」ものではなく、失禁時の処理を助けるものです。
3 「尿量を気にせずに, 1日中同じおむつを使うことができます」
【×】誤りです。おむつは衛生的に使用する必要があり、適切なタイミングでの交換が必要です。長時間交換しないと、皮膚トラブルや感染症の原因になります。
4 「おむつを着けると,安心して排泄ができます」
【×】誤りです。失禁を気にしている人にとってはおむつの使用は安心感につながりますが、羞恥心や不快感も伴います。あくまでもトイレでの排泄を促しましょう。
5 「家族の都合に合わせて,おむつを使いましょう」
【×】誤りです。本人の意向や尊厳を一番に考えるべきもので、家族の都合を優先するものではありません。
問題96
次の記述のうち,ポータブルトイレを使用するときの排泄の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ポータブルトイレの下に新聞紙を敷く。
2 ベッドで臥床している状態で,ズボンや下着をおろす。
3 ポータブルトイレには,前かがみになって座ってもらう。
4 排泄が終わるまで,ポータブルトイレの後ろに立って待つ。
5 排泄後の陰部の清拭は,ベッドの上で行う。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題96(解答と解説)
ポータブルトイレを使用した排泄の介護に関する問題です。
答えは、「3」です。
ポータブルトイレを使用した排泄介護では、利用者の尊厳・安全・快適さを保ちながら、適切な姿勢の保持と清潔保持を行うことが重要です。
1 ポータブルトイレの下に新聞紙を敷く。
【×】誤りです。新聞紙は衛生的とはいえず、滑って転倒するおそれもあります。専用の防水シートや吸水マットを使用することが望ましいです。
2 ベッドで臥床している状態で,ズボンや下着をおろす。
【×】誤りです。ポータブルトイレは起きて座って使うものです。ベッド上ではなく、ポータブルトイレまで移動したタイミングでズボンや下着をおろします。
3 ポータブルトイレには,前かがみになって座ってもらう。
【○】正しい選択肢です。排泄をスムーズに行うためには、軽く前かがみの姿勢が有効です。この姿勢は腹圧を高め、排泄を促す効果があります。
4 排泄が終わるまで,ポータブルトイレの後ろに立って待つ。
【×】誤りです。利用者のプライバシーに配慮し、必要がなければそばを離れて見守るのが基本です。必要な場合も、声かけや視線に注意してプライバシーを尊重しましょう。
5 排泄後の陰部の清拭は,ベッドの上で行う。
【×】誤りです。基本的にはポータブルトイレに座っているうちに清拭を行い、下着を整えたうえでベッドへ戻るのが適切です。
科目別過去問|11.生活支援技術
どんな問題もんだいが出でる?
この試験しけんの中なかで、最もっとも出題数しゅつだいすうが多おおい科目かもくです。
問題数も...