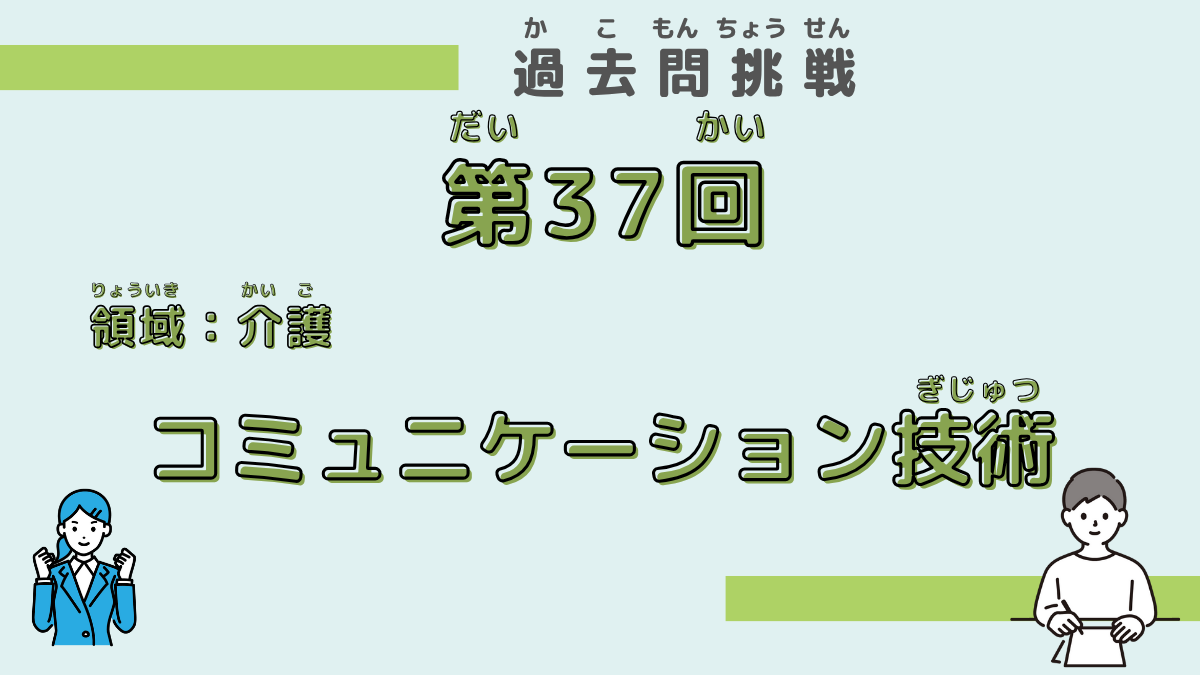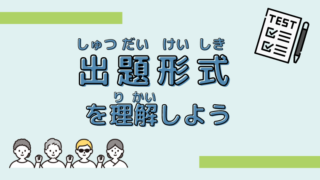コミュニケーション技術
問題74
次の記述のうち,利用者とのコミュニケーションの場面で用いる要約の技法として,適切なものを1つ選びなさい。
1 開かれた質問をして,利用者の気持ちを明らかにした。
2 共感しながら話を聞き,利用者の気持ちを受け止めた。
3 話の途中でうなずき,利用者の気持ちに同意した。
4 話の内容を総合的にまとめて返し,利用者の気持ちを整理した。
5 自己覚知を図り,利用者との人間関係の形成に努めた。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題74(解答と解説)
要約の技法に関する問題です。
答えは、「4」です。
要約とは、利用者が語った経験、行動、感情の経過を短くまとめることで気持ちや内容を整理し、共感と理解を示す重要なコミュニケーション技法です。
1 開かれた質問をして,利用者の気持ちを明らかにした。
【×】誤りです。開かれた質問は、利用者に自由に話をさせることで利用者の考えを深める質問の技法です。
2 共感しながら話を聞き,利用者の気持ちを受け止めた。
【×】誤りです。「共感的理解」の技法に関する記述です。
3 話の途中でうなずき,利用者の気持ちに同意した。
【×】誤りです。うなづきは、利用者に安心感を与える技法です。
4 話の内容を総合的にまとめて返し,利用者の気持ちを整理した。
5 自己覚知を図り,利用者との人間関係の形成に努めた。
【×】誤りです。自己覚知とは、自分自身の感情や行動、考え方の特徴を理解することです。利用者との人間関係の形成には大切なことですが、要約の技法のことではありません。
#要約 #自己覚知 #共感的理解
問題75
次の記述のうち,利用者と家族の意向が異なるとき,家族とのコミュニケーションにおいて介護福祉職が留意すべき点として,適切なものを1つ選びなさい。
1 家族に支援方針を決めてもらう。
2 家族を通して利用者の意向を聴き取る。
3 家族と話す機会を別に設ける。
4 家族にカウンセリングを行うことを意識する。
5 家族を説得する。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題75(解答と解説)
家族との関わり方に関する問題です。
答えは、「3」です。
介護福祉職は、利用者の意思を尊重しながら、家族とも良好な関係を保つ必要があります。
今回の問題では、家族と利用者の意向が異なるときに、どのような姿勢で関わるかが問われています。
1 家族に支援方針を決めてもらう。
【×】誤りです。介護はあくまで利用者本人の意思を尊重することが原則です。家族の意見を聞くことは大切ですが、支援方針を家族だけで決めるのは適切ではありません。
2 家族を通して利用者の意向を聴き取る。
【×】誤りです。利用者本人の意向は、本人から直接確認することが基本です。家族を通して聴き取ると、本人の意思が正しく反映されない恐れがあります。
3 家族と話す機会を別に設ける。
【○】正しい選択肢です。利用者と家族の意見が異なるときは、家族との個別の話し合いの機会を設けることが有効です。
4 家族にカウンセリングを行うことを意識する。
【○】正しい選択肢です。介護福祉職には専門的なカウンセリングの役割は求められていません。必要であれば、専門職につなぐようにします。
5 家族を説得する。
【×】誤りです。一方的に家族を説得することは、対立を生む原因になり、信頼関係の継続が難しくなります。利用者と家族の気持ちに寄り添い、話し合いを通じて調整していくことが大切です。
問題76
Aさん(80歳,男性,要介護3)は,介護老人福祉施設に入所している。アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer’s type)が進行している。ある日の昼食時,介護福祉職がAさんに配膳すると,「お金はこれしかありません。足りますか」と小さくたたまれたティッシュペーパーを渡してきた。
このときのAさんに対する介護福祉職の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ティッシュペーパーは,口の周りが汚れたら拭くものだと伝える。
2 ティッシュペーパーが不足しているサインとして受け止める。
3 飲食店での会計の場面であると認識して対応する。
4 食事に集中するように促す。
5 小遣いの増額を家族に相談する。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題76(解答と解説)
アルツハイマー型認知症の人への関わり方に関する問題です。
答えは、「3」です。
Aさんの言動から、認知症の中核症状である見当識障害が見受けられます。
脳の障害によるものなので、Aさんを否定することなく尊重し、対応することが大切です。
1 ティッシュペーパーは,口の周りが汚れたら拭くものだと伝える。
【×】誤りです。現実的な説明で本人の誤認識を否定する対応は、混乱や不安を招く原因になります。
2 ティッシュペーパーが不足しているサインとして受け止める。
【×】誤りです。本人はティッシュを「お金」と認識して渡しており、ティッシュの不足ではなく、飲食店での支払いという記憶や場面の混同と受け止めます。
3 飲食店での会計の場面であると認識して対応する。
【○】正しい選択肢です。Aさんは飲食店での支払いという記憶や場面の混同をしています。介護福祉職はその世界観を否定せず、やさしく受け止めて対応します。
4 食事に集中するように促す。
【×】誤りです。現実に引き戻すような対応ではなく、Aさんの気持ちに寄り添う姿勢が大切です。
5 小遣いの増額を家族に相談する。
【×】誤りです。Aさんは本当にお金を求めているわけではないので、適切ではありません。
#アルツハイマー型認知症 #見当識障害
問題77
構音障害のあるBさんは,現在発語訓練を実施中である。ある日,介護福祉職に対して,「おあんで,あつがおごれた」と訴えた。介護福祉職は,Bさんの発語をうまく聞き取れず,「もう一度,言ってください」と伝えた。Bさんは,自身の発語で会話を続けようとしているが,介護福祉職には,その内容を十分に理解することができなかった。
このときの,Bさんに対する介護福祉職の判断として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 Bさんは言葉の意味の理解に支障があるため,会話の継続は困難である。
2 発音が苦手なため,短い言葉でゆっくり話してもらう必要がある。
3 話す意欲があるため,開かれた質問が有効である。
4 発語訓練の効果がみられないため,訓練を中止する必要がある。
5 Bさんの言葉が聞き取れないため,会話を中断する必要がある。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題77(解答と解説)
構音障害の人への関わり方に関する問題です。
答えは、「2」です。
構音障害とは、口・舌・喉などの音声器官の運動機能障害によって、発音が不明瞭な(はっきりしない)障害です。
言葉の意味の理解は問題がないことが多いので、介護福祉職は利用者の話す意欲を感じとり、適切な対応をすることが大切です。
1 Bさんは言葉の意味の理解に支障があるため,会話の継続は困難である。
【×】誤りです。構音障害は「話すこと(発音)」の障害で、意味の理解や伝えたい気持ちに問題があるわけではありません。会話の継続をあきらめることは適切ではありません。
2 発音が苦手なため,短い言葉でゆっくり話してもらう必要がある。
3 話す意欲があるため,開かれた質問が有効である。
【×】誤りです。開かれた質問は、利用者が自由に話せますが、長くなりやすく、構音障害の人にとっては負担になります。選択肢を示す質問や短く答えられる質問(閉じられた質問)が有効です。
4 発語訓練の効果がみられないため,訓練を中止する必要がある。
【×】誤りです。発語訓練はすぐに効果が出るとは限りません。また、訓練の中止を介護福祉職の判断ですべきではありません。
5 Bさんの言葉が聞き取れないため,会話を中断する必要がある。
【×】誤りです。聞き取りにくくても、本人は一生懸命伝えようとしています。会話を中断することは、本人の話す意欲を失わせる可能性もあるため、適切ではありません。
問題78
Cさん(55歳,男性)は,知的障害がある。3か月前に,施設から居宅での一人暮らしに移行し,現在は,居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら生活している。ある日,Cさんが,「ゴミ,分けて捨てるの,難しいよ」と言うので,室内に分別収集の説明書を貼って,カレンダーに収集日を書くことにした。そして,介護福祉職は,「この説明書とカレンダーを見て,捨てるといいですよ」とCさんに伝えた。その後,Cさんは努力していたが,分別できなかったゴミが少しずつ増えていった。
次のうち,Cさんにかける介護福祉職の最初の言葉として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「ゴミでいっぱいになる前に,適切に捨てられるようになりましょう」
2 「説明書とカレンダーをよく見てください」
3 「ゴミが増えてきて,気持ち悪いですね」
4 「がんばっていれば,上手にできるようになりますよ」
5 「ゴミ捨ては難しいですよね。できることをいっしょに考えましょう」
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題78(解答と解説)
知的障害の人への関わり方に関する問題です。
答えは、「5」です。
知的障害のある利用者が在宅で自立した生活を送るためには、できていない点を責めるのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら、どうやったらできようになるのか、方法を一緒に考えていく姿勢が大切です。
共感的で前向きな声かけが求められます。
1 「ゴミでいっぱいになる前に,適切に捨てられるようになりましょう」
【×】誤りです。できていない点を指摘する内容であり、プレッシャーや責められている印象を与える可能性があるため、適切ではありません。
2 「説明書とカレンダーをよく見てください」
【×】誤りです。Cさんはゴミを捨てる努力はしているので、よく見たからといって解決できるものではないと考えられ、ほかの解決策を考える必要があります。
3 「ゴミが増えてきて,気持ち悪いですね」
【×】誤りです。環境状況について責めるような声かけをしても、解決にはつながりません。
4 「がんばっていれば,上手にできるようになりますよ」
【×】誤りです。一見励ましているように見えますが、努力だけを求めており、具体的な支援策が示されていないため、解決にはつながりません。
5 「ゴミ捨ては難しいですよね。できることをいっしょに考えましょう」
【○】正しい選択肢です。Cさんの「分別が難しい」という気持ちに寄り添い、一緒に方法を考えようという前向きな姿勢を示しています。最も適切な声かけです。
問題79
介護保険サービスにおける記録に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 記録に含まれないものとして食事チェック表がある。
2 介護記録は介護福祉職の意見を中心に記録する。
3 調査・研究目的で記録を利用することは避ける。
4 主観的情報と客観的事実は区別しないで記録する。
5 利用者は記録の閲覧を請求することができる。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題79(解答と解説)
介護記録に関する問題です。
答えは、「5」です。
介護記録は、サービスの質を高め、チームでの情報共有を円滑にする大切なものです。
今回の問題では、記録内容や管理の基本的なルール、個人情報の扱いについて正しく理解しているかが問われています。
1 記録に含まれないものとして食事チェック表がある。
【×】誤りです。食事チェック表は、利用者の摂取状況や健康状態を確認する大切な記録です。介護記録の一部として含まれます。
2 介護記録は介護福祉職の意見を中心に記録する。
【×】誤りです。介護記録は客観的な事実を中心に記録することが原則です。介護福祉職の意見を中心になると正確な情報共有ができなくなってしまいます。
3 調査・研究目的で記録を利用することは避ける。
【×】誤りです。個人が特定されないように配慮し、本人の同意など必要な手続きをとれば、記録を調査・研究に利用することは可能です。
4 主観的情報と客観的事実は区別しないで記録する。
【×】誤りです。主観と客観ははっきりと分けて記録することが大切です。
5 利用者は記録の閲覧を請求することができる。
【○】正しい選択肢です。介護記録は個人情報であり、本人やその家族には閲覧する権利があります。
#介護記録 #個人情報
科目別過去問|10.コミュニケーション技術
どんな問題もんだいが出でる?
ここでは、「人間関係にんげんかんけいとコミュニケーション」の科目かもくと異ことなり、実際じっさいに...