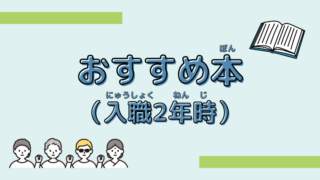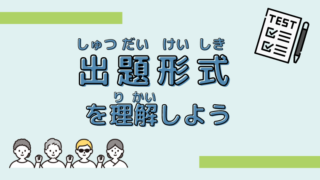発達と老化の理解
問題31
次の記述のうち,子どもの標準的な成長として,適切なものを1つ選びなさい。
1 1歳半から2歳ごろに,ハイハイをして移動できるようになる。
2 生後9か月から1歳ごろに,指をさして自分の関心や欲求を他者に伝えられるようになる。
3 子どもが使う言葉が急に増える語彙爆発は, 5歳を過ぎたころに生じる。
4 人見知りの反応は, 2歳を過ぎたころに生じる。
5 イヤイヤをしてすぐに泣く行動は,第二反抗期に生じる。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題31(解答と解説)
子どもの成長に関する問題です。
答えは、「2」です。
1 1歳半から2歳ごろに,ハイハイをして移動できるようになる。
【×】誤りです。ハイハイとは赤ちゃんが手のひらと膝を床につけたまま、お腹を床につけずに前に進む動作のことです。ハイハイは、生後7~10か月頃から始まります。
1歳半から2歳ごろは、ほとんどの子どもが歩き始めています。
2 生後9か月から1歳ごろに,指をさして自分の関心や欲求を他者に伝えられるようになる。
【○】正しい選択肢です。指さしは言葉が話せない赤ちゃんにとって、大切なコミュニケーション方法です。
3 子どもが使う言葉が急に増える語彙爆発は, 5歳を過ぎたころに生じる。
【×】誤りです。語彙爆発とは、新しい言葉を急激にたくさんの言葉を覚え、使い始めることです。語彙爆発は、1歳半から2歳ごろに生じます。
4 人見知りの反応は, 2歳を過ぎたころに生じる。
【×】誤りです。人見知りの反応は,生後6か月から8か月に始まります。
5 イヤイヤをしてすぐに泣く行動は,第二反抗期に生じる。
【×】誤りです。イヤイヤをしてすぐに泣く行動は、自我や自立が芽生える2歳ごろから始まります。これを第一次反抗期といいます。第二反抗期は、11歳から17歳頃の思春期に起こります。
問題32
次の記述のうち,神経性無食欲症(anorexia nervosa)に関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 活動性が高まる。
2 学童期に最も生じやすい。
3 太ることへの恐怖はみられない。
4 低体重の深刻さを理解している。
5 多くが男性である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題32(解答と解説)
神経性無食欲症に関する問題です。
答えは、「1」です。
神経性無食欲症は、やせたいという強い気持ちから食事を極端に制限し、食べることへの強い不安や体重増加への恐怖を感じてしまう心の病気です。
1 活動性が高まる。
【○】正しい選択肢です。やせている割には、活動性が高まり過剰な活動や運動をしてしまう特徴があります。
2 学童期に最も生じやすい。
【×】誤りです。学童期とは6~12歳のことです。12~15歳頃の思春期以降に発症しやすい状況です。
3 太ることへの恐怖はみられない。
【×】誤りです。太ることへの恐怖は強く見られるのが特徴です。
4 低体重の深刻さを理解している。
【×】誤りです。低体重の深刻さを理解していないため、低体重の危険性を理解できず、治療につながらないといった問題があります。
5 多くが男性である。
【×】誤りです。多くが10代の女性です。
問題33
Aさん(73歳,男性)は,会社の役員として勤めていたが,3年前に退職した。地域の老人クラブへの入会を勧められたが拒否している。毎年,敬老の日に記念品が配布されても,不快感を示して受け取らない。退職後も会社の状況を気にしていて,後輩とときどき連絡をとっている。Aさんは,身体が衰えることに強い不安を感じて,筋力トレーニングを毎日行っている。会社の後輩から,「いつも若々しいですね」と言われることに喜びを感じている。
ライチャード(Reichard, S.)による,引退後の男性の5つの適応タイプのうち,Aさんに相当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。
1 外罰(憤慨)型
2 内罰(自責)型
3 円熟(成熟)型
4 自己防衛(装甲)型
5 ロッキングチェアー(安楽椅子)型
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題33
ライチャードの性格分類に関する問題です。
答えは、「4」です。
まず、ライチャードの性格分類を整理しましょう。
ライチャードは高齢者の性格の特性を5つに分類しました。
ライチャードの高齢者の性格分類
適応型
1.円熟型
自分が年を取るということを自覚し、ありのままを受入れ、活動意欲が下がらないタイプ。定年退職後も自分で積極的に社会参加をし、周囲に負担をかけることなく自分で暮らしを楽しもうとできる。
2.ロッキングチェアー/安楽いす型(依存型)
自分が年を取るということを自覚し、受入れてはいるものの、他人に依存している受身タイプ。積極性はないものの、誘われれば新しいところへ参加し、気楽に生活を送ろうとする。
3.防衛型(装甲型)
老いることへの不安や恐怖を自ら活動することでコントロールし、自己防衛するタイプ。
責任感が強いため、無理をしてでも様々な活動してしまうこともある。
不適応型
4.外罰型(憤慨型)
自分の過去や老いを受入れることができないタイプ。失敗などの原因を自分ではなく、他人のせいにしてしまう。
5.内罰型(自責型)
自分の過去全体を失敗とみなし、その原因が自分にあると考えるタイプ。愚痴と後悔を繰り返すため、うつ病になりやすい。
次に、Aさんの状況を事例から整理していきます。
今回の事例でポイントになるのは、次の部分です。
1 外罰(憤慨)型
【×】誤りです。他人のせいにしている記述はありません。
2 内罰(自責)型
【×】誤りです。自分を責めているといった記述はありません。
3 円熟(成熟)型
【×】誤りです。老人クラブへの入会を拒否しているという記述から必ずしも退職後の生活をありのままに受入れられているとは考えらえません。
4 自己防衛(装甲)型
【○】正しい選択肢です。筋力トレーニングを毎日行っているという記述から、老いることへの不安があり、若さを保とうとをしていることや、後輩へ連絡をとっていることからも責任感の強さが読み取れます。
5 ロッキングチェアー(安楽椅子)型
【×】誤りです。老人クラブへの入会を拒否しているという記述から新しいところへ参加をし気楽な人生を送ろうとしているとは考えらません。また誰かに依存をしているような記述はありません。
問題34(解答と解説)
次の記述のうち,結晶性知能に関する説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 感覚や運動に基づく知能である。
2 過去に得た知識を活用して問題を解決する能力である。
3 40~50歳で急激に低下する。
4 知識や文化の影響よりも,生理的な老化の影響を受けやすい。
5 その場で新しい問題を解決する能力である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題34(解答と解説)
結晶性知能に関する問題です。
答えは、「2」です。
知能とは、知識を蓄積したり、いろいろなことを判断する能力のことです。
知能とは、「結晶性知能」と「流動性知能」の2つに分けられます。
結晶性知能とは、学習や経験によって身につく能力のことです。語彙力や常識、計算力などが含まれ、年齢を重ねても比較的保たれやすい特徴があります。
流動性知能とは、新しいことを覚えたり、新しい環境に適応する能力のことです。未知の問題を解決する能力や推論力が含まれ、若い時期に高く、加齢とともに低下しやすい特徴があります。
1 感覚や運動に基づく知能である。
【×】誤りです。結晶性知能とは関連がありません。
2 過去に得た知識を活用して問題を解決する能力である。
3 40~50歳で急激に低下する。
【×】誤りです。結晶性知能は年齢を重ねても比較的保たれやすい特徴があります。
4 知識や文化の影響よりも,生理的な老化の影響を受けやすい。
【×】誤りです。結晶性知能は、老化の影響を受けにくいと言われています。
5 その場で新しい問題を解決する能力である。
【×】誤りです。流動性知能に関する記述です。
問題35
次の記述のうち,加齢に伴う感覚機能の変化として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 皮膚感覚が敏感になる。
2 高音域の聴力が高まる。
3 暗順応の時間が延長する。
4 味覚が敏感になる。
5 嗅覚が敏感になる。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題35(解答と解説)
加齢に伴う感覚機能の変化に関する問題です。
答えは、「3」です。
加齢に伴い、さまざまな身体機能に変化が出てきます。
感覚機能には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・皮膚感覚があり、加齢に伴い低下していきます。
1 皮膚感覚が敏感になる。
【×】誤りです。皮膚感覚は鈍感になります。
2 高音域の聴力が高まる。
【×】誤りです。老人性難聴は、高音域から始まりまり、音がひずんで聞こえるようになります。
3 暗順応の時間が延長する。
【○】正しい選択肢です。暗順応とは、暗い場所に目が慣れて、だんだんと物が見えるようになることです。加齢に伴い、慣れるまでの時間が長くなります。
4 味覚が敏感になる。
【×】誤りです。味覚は鈍感になります。
5 嗅覚が敏感になる。
【×】誤りです。嗅覚は鈍感になります。
#感覚機能 #味覚 #嗅覚 #聴覚
問題36
Bさん(74歳,女性)は,地方で一人暮らしをしている。持病はなく,認知機能の異常もない。ダンスサークルに通い,近所との付き合いも良好で,今の暮らしに満足している。最近,白髪が増え,友人との死別もあり,年をとったと感じている。ある日,一人息子(50歳,未婚)から,東京で一緒に住むことを提案された。Bさんは,「ここには知り合いがいるが,東京には誰もいない。ここが一番いい」と言った。すると息子は,Bさんに,「年をとると頑固になる。あと数年したら認知症(dementia)になるかもしれないので,自分と一緒に暮らすべきだ」と言った。
次のうち,Bさんに関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 Bさんには,老性自覚はみられない。
2 Bさんには,友人との死別による悲嘆がみられる。
3 Bさんは,今,住んでいる環境や生活に適応できていない。
4 Bさんには,エイジズム(ageism)の考え方がみられる。
5 Bさんには,住み慣れた環境や仲間を喪失することへの不安がみられる。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題36(解答と解説)
Bさんの状況を正しく理解できているかを確認する問題です。
答えは、「5」です。
1 Bさんには,老性自覚はみられない。
【×】誤りです。老性自覚とは、自分が年を取ったことを自覚し、その変化を受け入れることです。「年をとったと感じている」という記述から、老性自覚はみられます。
2 Bさんには,友人との死別による悲嘆がみられる。
【×】誤りです。悲嘆とは、深い悲しみのことです。Bさんに関し、そのような記述はありません。
3 Bさんは,今,住んでいる環境や生活に適応できていない。
【×】誤りです。東京に住むことを提案されたときに、「ここが一番いい」と答えていることから、今の生活に適応できています。
4 Bさんには,エイジズム(ageism)の考え方がみられる。
【×】誤りです。エイジズムとは、高齢者に対する偏見や差別のことです。エイジズムの考え方がみられるのは、Bさんではなく息子さんの方です。
5 Bさんには,住み慣れた環境や仲間を喪失することへの不安がみられる。
【○】正しい選択肢です。Bさんは「ここが一番いい」というほど今の環境に満足しているなかで、友人との死別や息子からの引っ越しの提案など今の現状からの変化に不安が見られます。
問題37
次の記述のうち,サクセスフル・エイジング(successful aging)として,適切なものを1つ選びなさい。
1 長生きすることが,最大の目的である。
2 一人暮らしで,周囲の人と交流をしないようにしている。
3 膝に痛みがあるので,一日中ベッド上で過ごすようにしている。
4 難聴があるので,補聴器をつけてパソコン教室に通い始めた。
5 歌を上手に歌えなくなったので,カラオケに誘われても行かないようにしている。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題37(解答と解説)
サクセスフル・エイジングに関する問題です。
答えは、「4」です。
サクセスフル・エイジングとは、年をとっても心と体の健康を保ち、社会とのつながりを持ち続けながら、前向きに自分らしく生きていくことをいいます。
加齢を受容して、活動的に生きようとすることです。
1 長生きすることが,最大の目的である。
【×】誤りです。ただ長生きするのではなく、心と体の健康を保ち、充実した生活を送ることを大切にします。
2 一人暮らしで,周囲の人と交流をしないようにしている。
【×】誤りです。社会とのつながりも大切な要素です。
3 膝に痛みがあるので,一日中ベッド上で過ごすようにしている。
【×】誤りです。膝の痛みなども受け入れながら、前向きに活動的な生活を送ることが大切です。
4 難聴があるので,補聴器をつけてパソコン教室に通い始めた。
【○】正しい選択肢です。耳が聞こえないことを補聴器でカバーして活動的な生活を送っているので、適切な選択肢です。
5 歌を上手に歌えなくなったので,カラオケに誘われても行かないようにしている。
【×】誤りです。誘いを断るなど社会とのつながりを避けるのは、サクセスフル・エイジングの考え方ではありません。
問題38
次のうち,老年症候群に直接関わる疾患として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 高血圧症(hypertension)
2 糖尿病(diabetes mellitus)
3 骨粗鬆症(osteoporosis)
4 心筋梗塞(myocardial infarction)
5 脂質異常症(dyslipidemia)
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題38(解答と解説)
老年症候群に関する問題です。
答えは、「3」です。
老年症候群とは、高齢になることで起こりやすくなるさまざまな体や心の変化や機能の低下のことです。複数の原因が重なって起こることが多く、生活の質の低下や、要介護状態につながるため、早めの気づきと対応が大切です。
1 高血圧症(hypertension)
【×】誤りです。高血圧症とは、血圧が高い状態が持続することです。動脈硬化につながり、心疾患、脳疾患などを引き起こすリスクが高まりますが、老年症候群に直接関わる疾患ではありません。
2 糖尿病(diabetes mellitus)
【×】誤りです。糖尿病とは、インスリンの作用不足によって血中の血糖濃度が慢性的に高くなる病気です。心疾患や失明、腎不全などにつながるリスクがありますが、老年症候群に直接関わる疾患ではありません。
3 骨粗鬆症(osteoporosis)
【○】正しい選択肢です。骨粗鬆症は、骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症は、高齢者においては転倒による骨折リスクを高め、これにより生活機能の低下につながるため、老年症候群に直接関わる疾患です。
4 心筋梗塞(myocardial infarction)
【×】誤りです。心筋梗塞とは、心臓に血液を送る血管(冠動脈)がつまって、心筋(心臓の筋肉)に酸素が届かなくなり、一部の機能が死んでしまう病気です。心不全や不整脈を引き起こすリスクがありますが、老年症候群に直接関わる疾患ではありません。
5 脂質異常症(dyslipidemia)
【×】誤りです。脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪の値が高すぎたり、善玉コレステロールが少なすぎたりする状態です。動脈硬化につながり、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めますが、老年症候群に直接関わる疾患ではありません。
#老年症候群 #骨粗鬆症