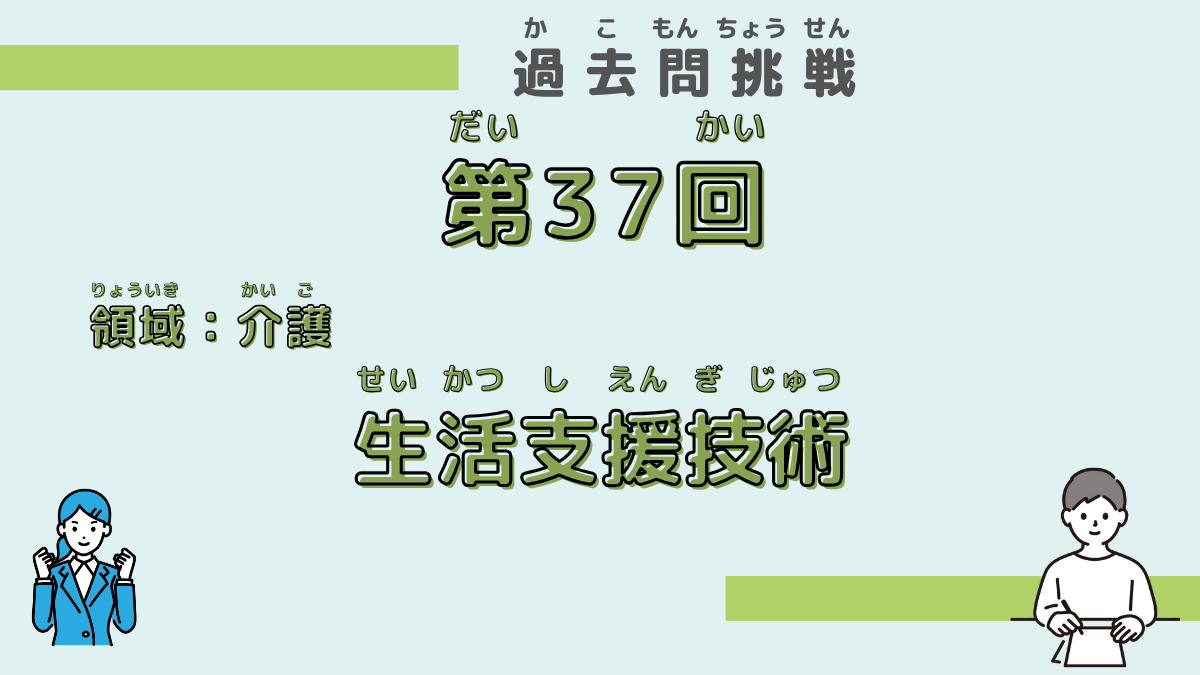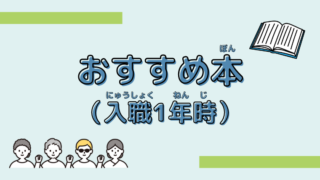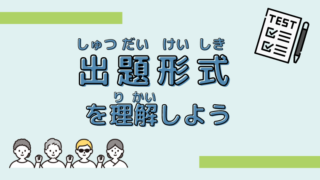解答と解説
問題92
入浴作用を生かした入浴介護に関する問題です。
答えは、「3」です。
入浴には、身体の清潔保持だけでなく、血行促進やリラックス効果、関節の可動域の向上など様々な作用があります。
特に試験でも問われやすい作用(効果)は、次の3つです。
- 温熱作用(効果)
- 浮力作用(効果)
- 静水圧作用(効果)
1 食事は,入浴直前に摂取する。
【×】誤りです。食事後すぐに入浴をすると、消化不良や貧血を起こすことがあります。食事と入浴の間は、最低でも30分~1時間は空けることが望ましいです。
2 高血圧の人には,42℃以上の湯につかってもらう。
【×】誤りです。42℃以上の熱い湯は、血圧の急上昇や心臓への負担がかかるため、高血圧の人には不適切です。
3 浴槽の中では,関節運動を促す。
【○】正しい選択肢です。浮力作用により、関節の動きが楽になり、痛みも軽減されるため、入浴中の軽い関節運動は高齢者にとって効果的です。
4 心疾患(heart disease)のある人には,肩まで湯につかってもらう。
【×】誤りです。心疾患のある人が肩まで湯につかると、心臓に大きな負担がかかり危険です。 湯量は胸の下あたりまでにし、半身浴などがおすすめです。
5 個浴の浴槽内では,足を浮かせてもらう。
【×】誤りです。浴槽内で足を浮かせると体が不安定になり、転倒や溺れるリスクが高くなります。足裏をしっかり浴槽の底につけるようにし、安定した姿勢を保つことが大切です。