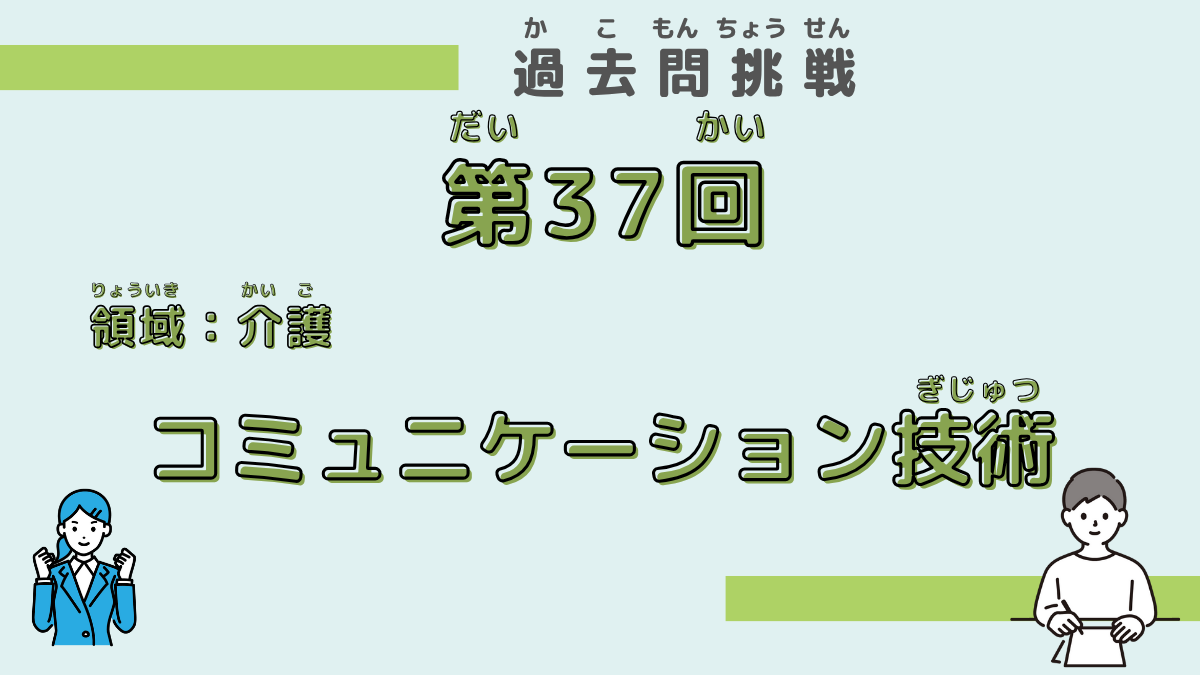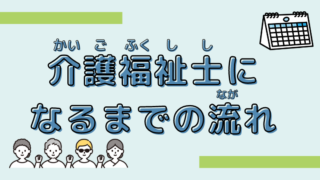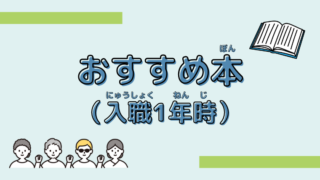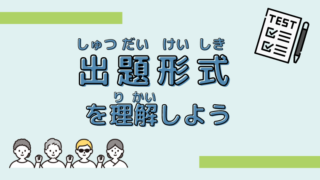コミュニケーション技術
試験用タイマー
開始ボタンを押すとタイマーがスタートします(目安時間:2分)
問題77
構音障害のあるBさんは,現在発語訓練を実施中である。ある日,介護福祉職に対して,「おあんで,あつがおごれた」と訴えた。介護福祉職は,Bさんの発語をうまく聞き取れず,「もう一度,言ってください」と伝えた。Bさんは,自身の発語で会話を続けようとしているが,介護福祉職には,その内容を十分に理解することができなかった。
このときの,Bさんに対する介護福祉職の判断として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 Bさんは言葉の意味の理解に支障があるため,会話の継続は困難である。
2 発音が苦手なため,短い言葉でゆっくり話してもらう必要がある。
3 話す意欲があるため,開かれた質問が有効である。
4 発語訓練の効果がみられないため,訓練を中止する必要がある。
5 Bさんの言葉が聞き取れないため,会話を中断する必要がある。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題77
構音障害の人への関わり方に関する問題です。
答えは、「2」です。
構音障害とは、口・舌・喉などの音声器官の運動機能障害によって、発音が不明瞭な(はっきりしない)障害です。
言葉の意味の理解は問題がないことが多いので、介護福祉職は利用者の話す意欲を感じとり、適切な対応をすることが大切です。
1 Bさんは言葉の意味の理解に支障があるため,会話の継続は困難である。
【×】誤りです。構音障害は「話すこと(発音)」の障害で、意味の理解や伝えたい気持ちに問題があるわけではありません。会話の継続をあきらめることは適切ではありません。
2 発音が苦手なため,短い言葉でゆっくり話してもらう必要がある。
3 話す意欲があるため,開かれた質問が有効である。
【×】誤りです。開かれた質問は、利用者が自由に話せますが、長くなりやすく、構音障害の人にとっては負担になります。選択肢を示す質問や短く答えられる質問(閉じられた質問)が有効です。
4 発語訓練の効果がみられないため,訓練を中止する必要がある。
【×】誤りです。発語訓練はすぐに効果が出るとは限りません。また、訓練の中止を介護福祉職の判断ですべきではありません。
5 Bさんの言葉が聞き取れないため,会話を中断する必要がある。
【×】誤りです。聞き取りにくくても、本人は一生懸命伝えようとしています。会話を中断することは、本人の話す意欲を失わせる可能性もあるため、適切ではありません。