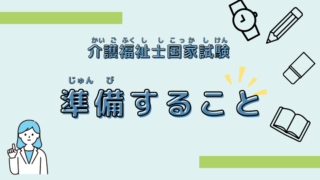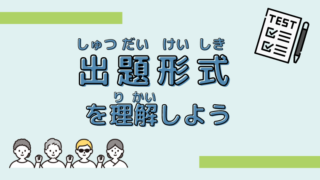介護の基本
試験用タイマー
開始ボタンを押すとタイマーがスタートします(目安時間:2分)
問題69
次の記述のうち,介護従事者を守る法制度として,正しいものを1つ選びなさい。
1 労働安全衛生法では,年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。
2 労働者災害補償保険法では,労働時間,賃金,休暇などの労働条件を定めている。
3 環境基本法では,快適な職場環境の形成の促進を定めている。
4 介護休業は,対象家族1名につき,毎年93日間を取得できる。
5 出生時育児休業は,子の出生後から8週間取得できる。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題69
介護従事者を守る法律に関する問題です。
答えは、「1」です。
ここ数年、介護福祉職の健康管理といった視点での問題が出題されるようになっています。
介護技術に関することはもちろん、法律についてもおさえましょう。
1 労働安全衛生法では,年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。
【○】正しい選択肢です。労働安全衛生法は、働く人が安全で健康に仕事ができるように、職場の環境を整えたり、ケガや病気を防ぐためのルールを決めた法律です。働く人の健康を守るために、会社は年に1回以上、健康診断を行わなければならないと決められています。
2 労働者災害補償保険法では,労働時間,賃金,休暇などの労働条件を定めている。
【×】誤りです。労働者災害補償保険法は、仕事中や通勤中のけがや病気、死亡に対して、労働者やその家族を支援することを目的とした法律です。労働条件を定めているのは、「労働基準法」です。
3 環境基本法では,快適な職場環境の形成の促進を定めている。
【×】誤りです。環境基本法は、空気や水、土などの自然を守ることを目的とした法律です。快適な職場環境については、「労働安全衛生法」で定められています。
4 介護休業は,対象家族1名につき,毎年93日間を取得できる。
【×】誤りです。介護休業は、対象家族1名につき、通算で93日間取得できます。毎年ではありません。
5 出生時育児休業は,子の出生後から8週間取得できる。
【×】誤りです。出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できます。