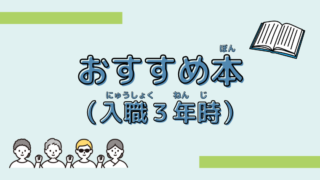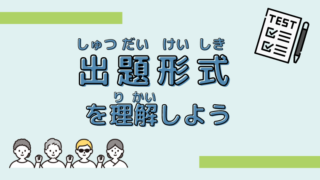社会の理解
試験用タイマー
開始ボタンを押すとタイマーがスタートします(目安時間:2分)
問題9
Aさん(48歳,会社員)は,うつ症状から体調不良が続き,仕事を休むことが増えたため,自主的に退職した。その後,体調は回復したが,再就職先がなかなか見つからなかった。しばらく貯金で生活していたが,数か月後,生活を営むことができなくなってしまった。頼れる親族はなく,生活保護を受給することにした。
この事例において,日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 団体交渉権
2 平等権
3 財産権
4 思想の自由
5 生存権
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題9
日本国憲法で保障された権利に関する問題です。
答えは、「2」です。
Aさんが受給した生活保護は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活をする権利」に基づいて作られた制度です。生活に困っている人に対して、国が生活費や医療費などを支給し、自立して生活できるように支援する仕組みです。
1 団体交渉権
【×】誤りです。団体交渉権は、労働者が働く条件をよくするために、労働組合を通して会社と話し合うことができる権利です。この権利は、憲法第28条で守られています。
2 平等権
【×】誤りです。平等権は、すべての人が法律のもとで平等にあつかわれ、人種や性別などに関係なく差別されない権利です。この権利は、憲法第14条に定められています。
3 財産権
【×】誤りです。財産権は、自分の財産を自由に持ったり、使ったり、売ったりすることができる権利です。この権利は、憲法第29条で定められています。ただし、社会全体の利益に反しないように、制限されることもあります。
4 思想の自由
【×】誤りです。思想の自由は、自分の考えや信じていることを自由に持つことができる権利です。この権利は、憲法第19条で定められています。ほかの人にむりに考えを変えさせられることはありません。
5 生存権
【○】正しい選択肢です。生存権は、すべての人が健康で文化的な最低限度の生活をする権利で、憲法第25条によって保障されています。生活保護制度は、生存権の理念に基づくものです。
#日本国憲法 #生活保護