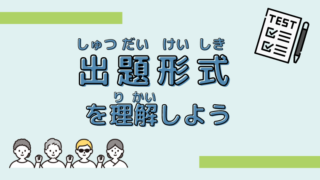社会の理解
問題7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 収益事業は禁止されている。
2 所轄庁は内閣府である。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
4 評議員会を置く必要がある。
5 解散は禁止されている。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題7(解答と解説)
社会福祉法人に関する問題です。
答えは、「4」です。
社会福祉法人は、保育所や特別養護老人ホーム、障害施設などを運営することを目的とした、営利を目的としない法人です。
営利を目的としない法人とは、利益を上げることよりも、社会に役立つ活動や社会問題の解決を目指して活動する法人のことです。
社会福祉法人は、評議員、理事、監事(規模が大きい法人では会計監査人も)によって構成されています。
また、社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、公益事業や収益事業も行うことができます。
1 収益事業は禁止されている。
【×】誤りです。収益事業は禁止されていません。
2 所轄庁は内閣府である。
【×】誤りです。所轄庁とは、特定の分野や団体を監督・管理する行政機関のことです。社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事または厚生労働大臣です。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
【×】誤りです。設立時には、所轄庁の認可が必要です。
4 評議員会を置く必要がある。
【○】正しい選択肢です。2017年の社会福祉法の改正で、評議員会の設置が義務づけられました。評議員は法人の運営を監督する役割を担います。
5 解散は禁止されている。
【×】誤りです。解散は禁止されていません。
#社会福祉法 #社会福祉法人
問題8
次の記述のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明として,正しいものを1つ選びなさい。
1 利用定員は,9人以下と定められている。
2 日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
3 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。
4 通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。
5 都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題8(解答と解説)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する問題です。
答えは、「2」です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護者が自宅で安心して生活できるよう、介護・看護が一体的に連携しながら、定期的に訪問し、必要に応じて随時対応するサービスです。24時間体制で支援が受けられます。
1 利用定員は,9人以下と定められている。
【×】誤りです。利用定員の定めはありません。
2 日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
3 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。
【×】誤りです。このサービスは訪問系サービスに位置づけられ、グループホームに入居する利用者に対するものではありません。
4 通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。
【×】誤りです。看護小規模多機能型居宅介護に関する説明です。
5 都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。
【×】誤りです。このサービスは地域密着型サービスに位置づけられ、市町村長が指定します。
#定期巡回・随時対応型訪問介護看護
問題9
Aさん(48歳,会社員)は,うつ症状から体調不良が続き,仕事を休むことが増えたため,自主的に退職した。その後,体調は回復したが,再就職先がなかなか見つからなかった。しばらく貯金で生活していたが,数か月後,生活を営むことができなくなってしまった。頼れる親族はなく,生活保護を受給することにした。
この事例において,日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 団体交渉権
2 平等権
3 財産権
4 思想の自由
5 生存権
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題9(解答と解説)
日本国憲法で保障された権利に関する問題です。
答えは、「2」です。
Aさんが受給した生活保護は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活をする権利」に基づいて作られた制度です。生活に困っている人に対して、国が生活費や医療費などを支給し、自立して生活できるように支援する仕組みです。
1 団体交渉権
【×】誤りです。団体交渉権は、労働者が働く条件をよくするために、労働組合を通して会社と話し合うことができる権利です。この権利は、憲法第28条で守られています。
2 平等権
【×】誤りです。平等権は、すべての人が法律のもとで平等にあつかわれ、人種や性別などに関係なく差別されない権利です。この権利は、憲法第14条に定められています。
3 財産権
【×】誤りです。財産権は、自分の財産を自由に持ったり、使ったり、売ったりすることができる権利です。この権利は、憲法第29条で定められています。ただし、社会全体の利益に反しないように、制限されることもあります。
4 思想の自由
【×】誤りです。思想の自由は、自分の考えや信じていることを自由に持つことができる権利です。この権利は、憲法第19条で定められています。ほかの人にむりに考えを変えさせられることはありません。
5 生存権
【○】正しい選択肢です。生存権は、すべての人が健康で文化的な最低限度の生活をする権利で、憲法第25条によって保障されています。生活保護制度は、生存権の理念に基づくものです。
#日本国憲法 #生活保護
問題10
次の記述のうち,保健所に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。
2 すべての市町村に設置の義務がある。
3 業務には精神保健に関する事項が含まれている。
4 歯科衛生士を置かなくてはならない。
5 児童の一時保護を行う。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題10(解答と解説)
保健所に関する問題です。
答えは、「3」です。
保健所は、地域保健法に定められた機関で、食品衛生、環境衛生、難病、精神保健、感染症予防、健康相談など住民に身近な保健サービスを行います。
1 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。
【×】誤りです。地域保健法に基づいて設置されています。
2 すべての市町村に設置の義務がある。
【×】誤りです。保健所は、47都道府県のほか、20指定都市、43中核市、23特別区に設置が義務づけられています。すべての市町村ではありません。
3 業務には精神保健に関する事項が含まれている。
4 歯科衛生士を置かなくてはならない。
【×】誤りです。歯科衛生士を置くことは義務ではありません。
5 児童の一時保護を行う。
【×】誤りです。児童の一時保護は、児童相談所の業務です。
問題11
地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 地域ケア会議の開催
2 施設サービスのケアプランの作成
3 成年後見制度の申請
4 介護認定審査会の設置
5 地域密着型サービスの事業者の指導・監督
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題11(解答と解説)
地域包括支援センターの業務に関する問題です。
答えは、「1」です。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、高齢者が地域で安心して生活できるよう健康相談や介護サービスの調整など包括的に支援をする施設です。
1 地域ケア会議の開催
【○】正しい選択肢です。地域ケア会議は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、医療・介護・福祉などの専門家が集まって、どのように支援するかや、どんなサービスを使うかを話し合う場です。地域包括支援センターの業務です。
2 施設サービスのケアプランの作成
【×】誤りです。施設サービスのケアプランの作成は、施設のケアマネジャーの業務です。
3 成年後見制度の申請
【×】誤りです。成年後見制度の申請(申立)は、本人や配偶者、4親等以内の親族、市町村長などができます。地域包括支援センターの業務は、権利擁護に関する相談・支援で、申請(申立)は業務ではありません。
4 介護認定審査会の設置
【×】誤りです。介護認定審査会は市町村が設置します。
5 地域密着型サービスの事業者の指導・監督
【×】誤りです。地域密着型サービスの事業者の指導・監督は、市町村の業務です。
#地域包括支援センター #地域ケア会議 #成年後見制度
問題12
Bさん(85歳,男性,要支援1)は,自宅で一人暮らしをしている。最近,物忘れが多くなり, 1か月前から地域支援事業の訪問型サービスを利用するようになった。ある日,Bさんが,「これからも自宅で生活したいが,日中,話し相手がいなくて寂しい」と介護福祉職に話した。
次のうち,Bさんに介護福祉職が勧めるサービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
2 介護老人福祉施設
3 第一号通所事業(通所型サービス)
4 夜間対応型訪問介護
5 居宅療養管理指導
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題12(解答と解説)
利用者に適したサービスを選ぶ問題です。
答えは、「3」です。
Bさんに適したサービスを選ぶために、おさえるポイントは次のとおりです。
- 85歳,男性,要支援1
- 現在は、地域支援事業の訪問型サービスを利用している
- 今後も自宅での生活を希望している
- 寂しいため、日中の話し相手がほしい
1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
【×】誤りです。Bさんは、要支援1であること、また自宅での生活を希望しているため、適切ではありません。
2 介護老人福祉施設
【×】誤りです。Bさんは、要支援1であること、また自宅での生活を希望しているため、適切ではありません。
3 第一号通所事業(通所型サービス)
【○】正しい選択肢です。第一号通所事業は要支援者に対する通いのサービスです。自宅での生活を希望しているBさんに最も適したサービスです。
4 夜間対応型訪問介護
【×】誤りです。Bさんは、日中の話し相手がほしいため、適切ではありません。
5 居宅療養管理指導
【×】誤りです。居宅療養管理指導とは、医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して療養上の管理、指導を行うサービスです。事例から医療的な管理が必要な部分は読み取れないため、適切ではありません。
#第一号通所事業(通所型サービス)
問題13
介護保険制度に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
2 第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
3 第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
5 介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題13(解答と解説)
介護保険制度に関する問題です。
答えは、「4」です。
介護保険制度の財源に関する基本的な知識です。
介護保険は保険のしくみで運営される社会保険です。
介護保険のお金は、保険料と公費(国や自治体などが税金で出すお金)でまかなわれています。
今回は、保険料に関する問題です。
1 第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
【×】誤りです。第1号被保険者の保険料は,市町村が徴収する。
2 第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
【×】誤りです。第1号被保険者の保険料は,市町村ごとに違います。
3 第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
【×】誤りです。第2号被保険者の保険料は,医療保険の保険料と合わせて徴収される。
4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
5 介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。
【×】誤りです。介護保険サービスの利用者負担割合は,2015年から収入に合わせて1割から3割になりました。
問題14
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
2 精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。
3 2024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
5 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題14(解答と解説)
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する問題です。
答えは、「1」です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、障害のある人が安定して働きやすくなるように作られた法律です。
企業には法定雇用率に基づいて、障害者を雇う義務があります。
また、仕事のときに特別な配慮をすることや、不公平な対応をしないことが決められています。
「法定雇用率」
会社が働く障害者をどれくらいの割合で雇うべきかを決めた数字のこと
1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
2 精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。
【×】誤りです。精神障害者も含まれます。
3 2024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。
【×】誤りです。従業員40人以上の事業主です。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
【×】誤りです。週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働も認められます。
5 2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。
【×】誤りです。2024年4月から一部の助成金が廃止されたため、同じではありません。
#障害者雇用促進法 #法定雇用率
問題15
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
2 短期入所は介護給付の1つである。
3 地域生活支援事業は,国が実施主体である。
4 自立支援給付は応益負担である。
5 行動援護は訓練等給付の1つである。
(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題15(解答と解説)
障害者総合支援法のサービスに関する問題です。
答えは、「2」です。
障害者総合支援法は、障害者や難病患者の自立生活と社会参加を支援するための法律です。
障害の種類や程度に応じて、相談支援や介護サービス、就労支援などの必要な支援を提供します。
障害者総合支援法のサービス
自立支援給付(応能負担)
障害のある人が、生活や社会での活動のために必要なサービス(介護、訓練、医療など)を使うとき、そのお金の一部を国や市などが出してくれる制度です。次のような給付があります。
- 介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所など)
- 訓練等給付 (自立訓練、就労移行支援、自立生活援助、共同生活援助など)
- 自立支援医療 (更生医療、育成医療など)
- 相談支援
- 補装具
地域生活支援事業
障害のある人が、自分で生活したり、社会の中で活動できるようにするための事業です。市町村が中心になって、その地域に合わせて行われます。
1 介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
【×】誤りです。介護給付費の支給を受けるためには、原則として障害支援区分(1~6)の認定が必要です。
2 短期入所は介護給付の1つである。
3 地域生活支援事業は,国が実施主体である。
【×】誤りです。地域生活支援事業の実施主体は市町村です。
4 自立支援給付は応益負担である。
【×】誤りです。自立支援給付は応能負担です。
5 行動援護は訓練等給付の1つである。
【×】誤りです。行動援護は、介護給付の1つです。
#障害者総合支援法 #自立支援給付 #介護給付
問題16
障害児支援に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。
2 放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。
3 障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。
4 障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。
5 保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題16(解答と解説)
障害児支援に関する問題です。
答えは、「5」です。
1 サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。
【×】誤りです。療育手帳は、知的機能の障害が18歳までに現れ、日常生活に支障がある人が取得できる手帳です。障害児支援には、必ずしも療育手帳の取得は必要ではありません。
2 放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。
【×】誤りです。子ども・子育て支援法は、すべての子どもが健やかに育ち、保護者が安心して子育てできるよう、教育・保育や地域の子育て支援を整える法律です。放課後等デイサービスは、障害者総合支援法に基づくサービスです。
3 障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。
【×】誤りです。障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、障害のある児童や発達に心配がある児童が直接事業所に通うことで、様々なサービスを受けられる事業です。利用するには、障害児支援利用計画の作成が必要です。
4 障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。
【×】誤りです。障害児入所支援は、児童福祉法に基づき、障害のある子どもが専門の施設に入って、生活の支援や訓練、必要な医療を受けながら、自立した生活を目指すための支援です。実施主体は、都道府県です。
5 保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。
【○】正しい選択肢です。児童福祉法に基づく支援の1つです。
問題17
次の記述のうち,サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
2 65歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。
3 認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。
4 食事サービスの提供が義務づけられている。
5 介護サービスの提供が義務づけられている。
(注)「高齢者住まい法」とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題17(解答と解説)
サービス付き高齢者向け住宅に関する問題です。
答えは、「1」です。
サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者住まい法」に基づき、高齢者が安心して暮らせるように、バリアフリーの住まいと安否確認・生活相談などのサービスがついた賃貸住宅です。
1 「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
2 65歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。
【×】誤りです。市町村の措置によって入居するものではなく、自由契約で入居できます。
3 認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。
【×】誤りです。認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に関する説明です。
4 食事サービスの提供が義務づけられている。
【×】誤りです。食事サービスの提供は義務ではありません。
5 介護サービスの提供が義務づけられている。
【×】誤りです。介護サービスの提供は義務ではありません。介護サービスが必要な人は、訪問介護などを別に契約することになります。
#サービス付き高齢者向け住宅
問題18
Cさん(60歳,男性)は,休日に自宅で趣味の家庭菜園の作業中に脳出血(cerebral hemorrhage)を起こして救急搬送された。特に麻痺はなく,その後,リハビリテーション病院に転院した。現在は,高次脳機能障害(higher brain dysfunction)の治療とリハビリテーションに専念している。
医療費を支払うときにCさんが利用する制度として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 介護保険制度
2 労働者災害補償保険制度
3 雇用保険制度
4 医療保険制度
5 年金制度
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題18(解答と解説)
医療費制度に関する問題です。
答えは、「4」です。
1 介護保険制度
【×】誤りです。介護保険制度の利用は原則65歳以上の人が対象です。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、特定疾病が原因で介護が必要な場合、介護保険を利用することができますが、高次脳機能障害は、特定疾病ではないため、対象にはなりません。
2 労働者災害補償保険制度
【×】誤りです。労働者災害補償保険制度は、いわゆる労災保険といわれるもので、仕事中や通勤中のけがや病気に対して、国が治療費や休業補償などを行う制度です。Cさんは仕事中の病気ではないため、対象ではありません。
3 雇用保険制度
【×】誤りです。雇用保険制度は、仕事を失ったときや育児・介護で働けないときにに生活を支えるお金を受け取れたり、教育訓練を受けられる制度です。
4 医療保険制度
【○】正しい選択肢です。医療費の支払いは、医療保険制度を利用します。
5 年金制度
【×】誤りです。年金制度は、年をとったり、障害で働けなくなったときなどに、生活を支えるお金を受け取れるしくみです。
#医療保険制度 #高次脳機能障害