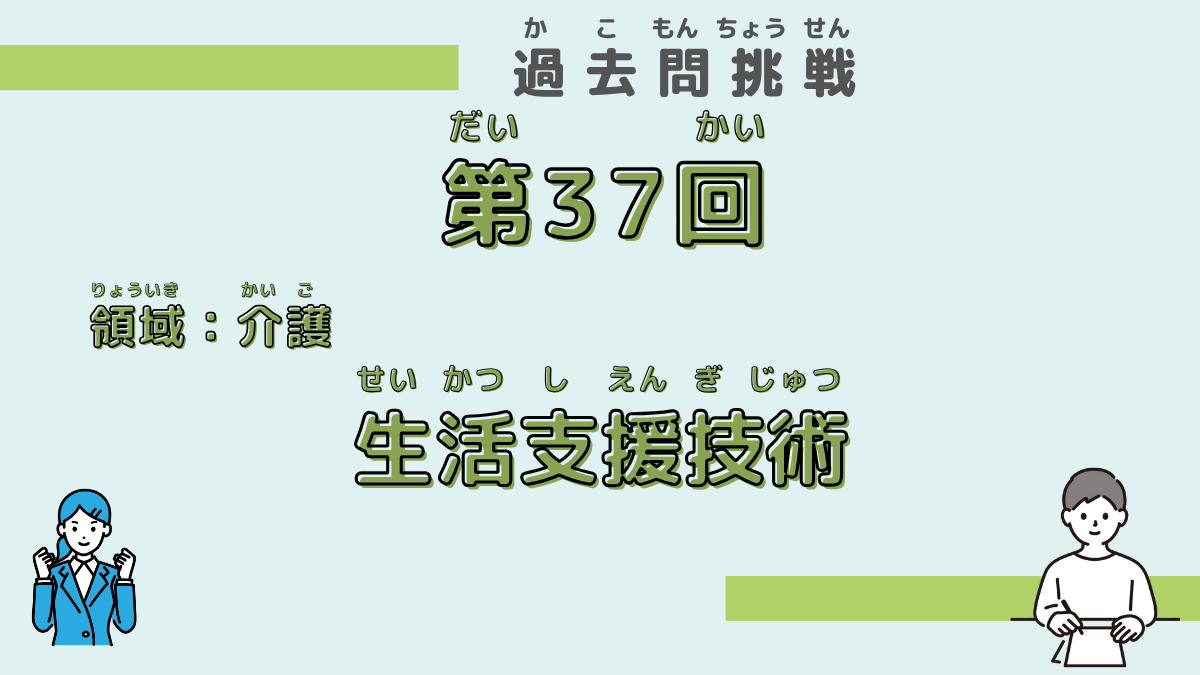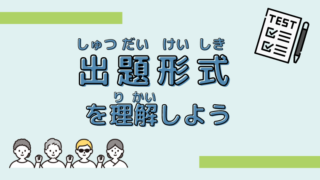解答と解説
問題105
情報・意思疎通支援用具に関する問題です。
答えは、「2」です。
脳性麻痺とは、受精から出生直後(生後4週まで)の脳の損傷により、運動機能の障害が生じる病気です。
手足がこわばって硬くなる「痙直型」と、不随意運動が生じる「アテトーゼ型」、バランスがとりにくい「失調型」、「混合型」に分類されます。
アテトーゼ型脳性麻痺では、手指の細かい動きや発音に困難がありますが、聴覚は保たれています。
このため、音声によるやり取りが難しい人の意思疎通を補う適切な用具を選びます。
1 福祉電話
【×】誤りです。高齢者や身体が不自由な人のための電話機で、ボタンが大きかったり、緊急通報機能や聞こえやすいように音量を調整する機能などが付いているものなどがあります。通話自体には明瞭な発音が必要となる場合が多く、Cさんには適していません。
2 携帯用会話補助装置
【○】正しい選択肢です。携帯用会話補助装置は、文字や記号を入力すると音声に変換して伝えられる機器です。発音が難しいCさんが、自分の意思を相手に伝えるのに有効です。
3 人工喉頭
【×】誤りです。人工喉頭は、喉頭摘出などで声が出せない人が使用する発声補助器です。Cさんは発声は可能なので、適切ではありません。
4 助聴器
【×】誤りです。助聴器は、聴覚が低下している人の聞こえを補うための機器です。Cさんは音の聞き取りはできるので、適切ではありません。
5 点字器
【×】誤りです。点字器は、視覚障害者が文字を読み書きするための道具です。Cさんの課題は視覚ではないため、適切ではありません。