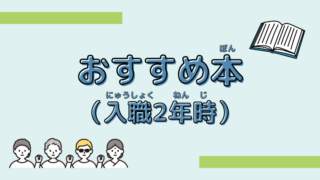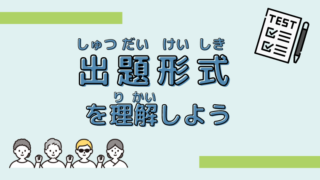こころとからだのしくみ
問題19
次のうち,恐怖や不安,喜びなどの情動に関わる脳の機能局在の部位として,正しいものを1つ選びなさい。
1 扁桃体
2 小脳
3 下垂体
4 海馬
5 視床下部
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題19(解答と解説)
脳の機能局在に関する問題です。
答えは、「1」です。
脳は各部位によってさまざまな機能(働き)があります。これを「脳の機能局在」と言います。
各選択肢の働きもしっかりと整理しましょう。
1 扁桃体
【○】正しい選択肢です。扁桃体は、脳の中で「感情」を感じたりコントロールしたりする場所です。特に「恐怖」や「不安」に強く関係しています。また、危険をすばやく見つけたり、感情に関係する記憶をつくったりする働きもあります。
2 小脳
【×】誤りです。小脳は、脳の後ろの下のほうにある部分で、体のバランスをとったり、動きをなめらかにしたりする働きをしています。手や足などをスムーズに動かすために大切で、歩く、走る、字を書くなどの動作を正確にコントロールします。
3 下垂体
【×】誤りです。下垂体は、脳の下のほうにある小さな器官で、体の成長や性ホルモン、ストレスへの反応、尿の量などをコントロールするホルモンを出しています。また、他の内分泌の器官(たとえば甲状腺や副腎)に「ホルモンを出しなさい」と命令を出す役目もあります。体の働きをバランスよく保つために、とても大切な場所です。
4 海馬
【×】誤りです。海馬は、脳の奥にある部分で、「記憶をつかさどる場所」として知られています。特に、新しいことを覚えるときに働きます。例えば、人の名前を覚えたり、どこかへ行った道順を覚えたりするときに海馬が使われます。過去の出来事を思い出すことにも関係していて、学習や記憶にとって大切な場所です。
5 視床下部
【×】誤りです。視床下部は、脳の真ん中あたりにある小さな部分で、体のいろいろな働きを調整しています。例えば、体温調整や食欲、睡眠などをコントロールしています。また、自律神経の働きも調整していて、心と体のバランスを保つ大事な役割をしています。
問題20
次のうち,顔の感覚に関与する脳神経として,正しいものを1つ選びなさい。
1 嗅神経
2 三叉神経
3 顔面神経
4 迷走神経
5 舌下神経
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題20(解答と解説)
顔の感覚に関与する脳神経に関する問題です。
答えは、「2」です。
各選択肢の働きもしっかりと整理しましょう。
1 嗅神経
【×】誤りです。嗅神経は、においを感じる神経です。鼻の中にあるにおいのセンサーが、においの情報をキャッチして、この神経を通じて脳に伝えます。
2 三叉神経
【○】正しい選択肢です。三叉神経は、顔の感覚やかむ動きをつかさどる大切な神経です。顔の皮膚の感覚(痛み・温度・触った感じ)を脳に伝えたり、咀嚼筋(かむ筋肉)を動かしたりします。顔の中でも特に広い範囲を担当する神経です。
3 顔面神経
【×】誤りです。顔面神経は、顔の表情をつくる筋肉を動かしたり、涙や唾液を出す働きを助けたりする神経です。また、舌の前のほうの味覚も感じ取る働きがあります。
4 迷走神経
【×】誤りです。迷走神経は、体のさまざまな器官とつながっている神経で、特に内臓の働きを調整します。心臓の動きや呼吸、消化などに影響を与え、自律神経の調整を行う大事な神経です。
5 舌下神経
【×】誤りです。舌下神経は、舌の動きをコントロールする神経です。食べるときや話すときに舌を動かすのに必要で、舌の筋肉を動かす働きをします。
問題21
次の記述のうち,鼻の構造と機能として,適切なものを1つ選びなさい。
1 鼻腔は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。
2 鼻毛は塵や埃を除去する。
3 鼻腔の奥は喉頭に直接つながっている。
4 鼻腔には毛細血管は少ない。
5 嗅細胞は外鼻孔にある。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題21(解答と解説)
鼻の構造に関する問題です。
答えは、「2」です。
1 鼻腔は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。
【×】誤りです。鼻腔は、上鼻道、中鼻道、下鼻道に分かれます。
2 鼻毛は塵や埃を除去する。
3 鼻腔の奥は喉頭に直接つながっている。
【×】誤りです。鼻腔の奥で直接つながっているのは、咽頭です。
4 鼻腔には毛細血管は少ない。
【×】誤りです。鼻腔には、非常に多くの毛細血管が通っています。毛細血管が広がったり、せまくなったりすることで、鼻の中の粘膜もふくらんだり、小さくなったりし、鼻づまりなどがおきます。
5 嗅細胞は外鼻孔にある。
【×】誤りです。嗅細胞は、においを感じ取る鼻の中の細胞で、鼻腔の奥にあります。外鼻孔は、鼻の穴のことで、空気が体の中に入る入口です。
問題22
次のうち,歯周病(periodontal disease)の症状として,適切なものを1つ選びなさい。
1 歯のくぼみの形成
2 歯の硬組織の軟化
3 歯髄の炎症・疼痛
4 歯のエナメル質の侵蝕
5 歯周ポケットの形成
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題22(解答と解説)
歯周病に関する問題です。
答えは、「5」です。
歯周病は、歯を支えている歯ぐきや骨に炎症が起きる病気です。ひどくなると、歯がぐらぐらして、抜けてしまう原因になります。
プラーク(歯垢)が原因で、初めは歯ぐきが赤く腫れて「歯肉炎」になり、進むと骨まで壊す「歯周炎」になります。
あまり痛みがなく、気づきにくいのが特徴です。
1 歯のくぼみの形成
【×】誤りです。歯のくぼみの形成は、歯の表面に穴や凹みができることです。虫歯が進行すると、歯のエナメル質が溶けてくぼみが現れます。歯周病の症状ではありません。
2 歯の硬組織の軟化
【×】誤りです。歯の硬組織の軟化とは、エナメル質や象牙質など、硬い部分が虫歯などで弱くなり、軟らかくなることです。これが進むと歯が削れたり、虫歯の原因となります。
3 歯髄の炎症・疼痛
【×】誤りです。歯髄の炎症・疼痛とは、歯の中にある神経(歯髄)が、虫歯やけがが原因で炎症を起こし、ズキズキと強い痛みが出ることです。歯周病では歯髄の炎症が起こることはほとんどありません。
4 歯のエナメル質の侵蝕
【×】誤りです。歯のエナメル質の侵蝕は、歯の表面にある一番外側の硬い部分(エナメル質)が、酸や虫歯の進行で削られたり溶けたりすることです。虫歯の原因となるもので、歯周病とは関係がありません。
5 歯周ポケットの形成
【○】正しい選択肢です。歯周ポケットの形成は、歯と歯ぐきの間に溝ができることです。歯周病が進行すると、歯ぐきが炎症を起こして腫れ、歯と歯ぐきの隙間が深くなります。この溝が歯周ポケットです。放置すると、さらに悪化することがあります。
問題23
Aさん(78歳,女性)は,友人から口臭を指摘されて悩んでいる。また,食事をするときに,「水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」とも話している。Aさんに歯の欠損,麻痺はなく,ストレスの訴えもない。
次のうち,Aさんのからだの中で,機能低下が考えられるものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 咀嚼
2 蠕動運動
3 嗅覚
4 唾液分泌
5 胃液分泌
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題23(解答と解説)
口臭に関する問題です。
答えは、「4」です。
口臭は誰でも気になるものす。口臭が強いと気になってコミュニケーションを取りたがらなくなる人もいます。
今回は、「口臭」と「飲み込みにくい」という症状の関連を問われています。
まず、口臭の原因は大きく分けると4つあります。
口臭の原因
体に原因があるもの
内臓など体に原因がある場合で、消化不良、肝機能の低下、糖尿病など疾患が原因になるもの
口の中に原因があるもの
舌苔という舌の汚れや、歯の汚れ、虫歯、歯周病などが原因になるもの
食べ物などが原因になるもの
にんにく、キムチなど臭いの強い食べ物、喫煙などが原因になるもの
生理的なもの
水分不足の状態など、唾液の分泌量が少ないことが原因となるもの(起床時など)
この原因と飲み込みにくさに関連がある選択肢を見つけていきます。
1 咀嚼
【×】誤りです。咀嚼とは、食べ物を歯でかみくだき、飲み込みやすくすることです。Aさんに歯の欠損,麻痺はないとの記述から、咀嚼機能の低下は考えにくいです。
2 蠕動運動
【×】誤りです。蠕動運動とは、消化管が波のように動いて食べ物を運ぶ働きです。Aさんは「水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」という自覚症状があるため、蠕動運動の機能低下は考えにくいです。
3 嗅覚
【×】誤りです。嗅覚とは、鼻でにおいを感じ取る感覚のことです。口臭は嗅覚で感じ、不快に感じることはあっても、それが食べものを飲み込みにくくする原因になるとは、あまり考えられません。
4 唾液分泌
【○】正しい選択肢です。「水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」という記述からも、唾液分泌の機能低下が考えられます。
5 胃液分泌
【×】誤りです。胃液分泌の機能低下は、消化に影響を与えます。消化不良が口臭につながることがあっても、それが食べものを飲み込みにくくする原因になるとは、あまり考えられません。
問題24
皮膚の構造に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 表皮の厚さは平均2.0mmである。
2 真皮には角質層がある。
3 外界と接する組織は表皮である。
4 皮脂腺は皮下組織にある。
5 表皮の最表面は基底層である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題24(解答と解説)
皮膚の構造に関する問題です。
答えは、「3」です。
.png)
1 表皮の厚さは平均2.0mmである。
【×】誤りです。表皮の厚さは平均0.1~0.2mmです。
2 真皮には角質層がある。
【×】誤りです。角質層は表皮にあります。
3 外界と接する組織は表皮である。
【○】正しい選択肢です。表皮は外界と接する組織で、外界の環境から体を守る働きをしています。
4 皮脂腺は皮下組織にある。
【×】誤りです。皮脂腺は真皮にあります。
5 表皮の最表面は基底層である。
【×】誤りです。表皮の最表面は角質層で、基底層は表皮の一番深いところにあります。
問題25
次のうち,高齢者が嗜好や温度覚の低下によって高温浴を希望した場合に,説明すべき高温浴の特徴として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 血圧の上昇
2 腸蠕動の促進
3 腎機能の促進
4 副交感神経の亢進
5 心機能の抑制
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題25(解答と解説)
高温浴の特徴に関する問題です。
答えは、「1」です。
問題にあるように、高齢者は温度を感じる力(温度覚)が弱くなっていて、お湯の温度がぬるく感じることがあります。そのため、高温浴を好む人もいます。
でも、高温浴は体に大きな負担がかかるので、なぜ危ないのかをよく知っておくことが大切です。
1 血圧の上昇
【○】正しい選択肢です。高温浴で血管が拡張し、血圧が上昇します。
2 腸蠕動の促進
【×】誤りです。高温浴では、腸の動きは抑制されます。
3 腎機能の促進
【×】誤りです。高温浴では、腎機能は抑制されます。
4 副交感神経の亢進
【×】誤りです。亢進とは、体の働きや反応がいつもより強くなることです。高温浴では、副交感神経ではなく、交感神経が活発化します。
5 心機能の抑制
【×】誤りです。高温浴では心機能は促進されます。これにより、心拍数が増加し、体に負担をかけてしまいます。
問題26
次のうち,食物の栄養素の大部分を吸収する部位として,正しいものを1つ選びなさい。
1 胃
2 小腸
3 直腸
4 横行結腸
5 S状結腸
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題26(解答と解説)
栄養素の吸収と消化管の働きに関する問題です。
答えは、「2」です。
1 胃
【×】誤りです。胃は、食物を消化する働きをします。
2 小腸
【○】正しい選択肢です。小腸は、十二指腸・空腸・回腸に分かれ、胃や十二指腸で消化された食物をさらに分解し栄養を吸収する働きをします。
3 直腸
【×】誤りです。直腸は、便をためて体の外に出す準備をする働きをします。
4 横行結腸
【×】誤りです。横行結腸は、食物の残りものから水分やミネラルを吸収する働きをします。
5 S状結腸
【×】誤りです。S状結腸は、便を一時的にためて、排便の準備をするはたらきをします。
問題27
次の記述のうち,レム睡眠に関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 記憶を整理し,定着させる。
2 脳を休息させる。
3 入眠初期に出現する。
4 成長ホルモンの分泌を促す。
5 深い眠りの状態である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題27(解答と解説)
睡眠に関する問題です。
答えは、「1」です。
-1.png)
レム睡眠は、眠っている間に目が速く動き、脳が起きているときのように活動している睡眠のことです。
この時期は夢を見やすく、体の筋肉はゆるんで動きにくくなっています。
レム睡眠は、記憶の整理や感情の調整に大切な役割を果たしています。
レム睡眠とノンレム睡眠とおおよそ90分の感覚で交互に繰り返されます。
1 記憶を整理し,定着させる。
【○】正しい選択肢です。レム睡眠は、脳がよく働く状態で、記憶を整理、定着させます。
2 脳を休息させる。
【×】誤りです。脳の休息は、ノンレム睡眠のときです。
3 入眠初期に出現する。
【×】誤りです。入眠は、ノンレム睡眠から始まります。
4 成長ホルモンの分泌を促す。
【×】誤りです。成長ホルモンは、ノンレム睡眠時に多く分泌されます。
5 深い眠りの状態である。
【×】誤りです。レム睡眠は浅い眠りの状態です。
問題28
Bさん(76歳,男性)は,この数週間,日中に,「眠い」と訴えている。Bさんは毎日15時にコーヒー1杯を飲み,たばこを1本吸い,21時に就寝する。夜間の睡眠状態を数日間観察すると,睡眠中にぴくぴくと下肢が動いていることがたびたびあった。起床後,手足に異常を感じるかをBさんに確認したが,「特にない」
とのことだった。
次のうち,Bさんの睡眠障害の原因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ニコチン摂取
2 レム睡眠行動障害
3 レストレスレッグス症候群
4 カフェイン摂取
5 周期性四肢運動障害
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題28(解答と解説)
睡眠障害に関する問題です。
答えは、「5」です。
Bさんの睡眠中の特徴は「ぴくぴくと下肢が動いていることがたびたびある」ことです。
これに当てはまる睡眠障害の選択肢を確認していきましょう。
1 ニコチン摂取
【×】誤りです。ニコチンには覚醒作用がありますが、1本程度ですので、睡眠障害に影響しているとは考えにくいです。
2 レム睡眠行動障害
【×】誤りです。レム睡眠行動障害は、レム睡眠中に体が動いてしまい、夢に合わせて叫んだり暴れたりする睡眠障害です。Bさんの特徴とは異なります。
3 レストレスレッグス症候群
【×】誤りです。レストレスレッグス症候群は、主に夜間、脚にムズムズする不快感を感じ、動かしたくなる病気です。Bさんの特徴とは異なります。
4 カフェイン摂取
【×】誤りです。カフェインには覚醒作用があるため、寝る前の摂取は控えたほうがいいですが、Bさんの特徴と関連があるとは考えにくいです。
5 周期性四肢運動障害
【○】正しい選択肢です。周期性四肢運動障害は、睡眠中に無意識に足や腕が繰り返し動くことで睡眠が妨げられる障害です。本人は気づきにくいですが、日中の眠気や集中力低下の原因となります。
問題29
次のうち,呼吸中枢がある部位として,正しいものを1つ選びなさい。
1 大脳
2 中脳
3 小脳
4 延髄
5 脊髄
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題29(解答と解説)
呼吸中枢に関する問題です。
答えは、「4」です。
呼吸中枢は、脳の延髄にある呼吸をコントロールする部分で、無意識に息を吸ったり吐いたりするリズムを調整しています。
血液中の酸素や二酸化炭素の量を感知して、呼吸の速さや深さを自動で調節します。
1 大脳
【×】誤りです。大脳は、運動、感覚、記憶、視覚認知などいろいろな働きを調整しています。
2 中脳
【×】誤りです。中脳は、体のバランス、姿勢の保持、視覚などを調整しています。
3 小脳
【×】誤りです。小脳は、平衡機能、姿勢反射、随意運動など体の運動を調節しています。
4 延髄
5 脊髄
【×】誤りです。脊髄は、脳と体をつなぎ、動きや感覚の情報を伝える働きをしています。
問題30
次のうち,脳の機能停止を示す徴候に該当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。
1 呼吸不全
2 溢流性尿失禁
3 心停止
4 蠕動運動の減弱
5 瞳孔散大・対光反射消失
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題30(解答と解説)
脳の機能停止(脳死)に関する問題です。
答えは、「5」です。
脳死とは、脳幹を含む脳の機能がほぼ完全に失われ回復不可能な状態です。
「法律的な死」ともいいます。
脳が働かなくなったことを示す「脳死」の基準がすべて当てはまり、臓器提供の意思が確認できれば、脳死を人の死と認めることができます。
脳死判定の基準(ポイント)
- 深い昏睡状態(目を開けたり、呼びかけに反応したりしない、深い眠りのような状態)
- 自発呼吸がない
- 瞳孔が開き、光に反応しない
- 脳幹反射(目や顔、のどの反射)がすべて消失している
- 一定時間をあけて、2回の判定を行う(通常6時間後など)
1 呼吸不全
【×】誤りです。呼吸不全は必ずしも脳の機能停止(脳死)とは限りません。
2 溢流性尿失禁
【×】誤りです。溢流性尿失禁は膀胱に尿がたまりすぎて少しずつ漏れてしまう状態です。脳の機能停止(脳死)とは関係はありません。
3 心停止
【×】誤りです。心停止は心臓が止まることです。心停止は、脳の機能停止(脳死)の判定基準にはなりません。
4 蠕動運動の減弱
【×】誤りです。蠕動運動の減弱とは、食べ物を腸の中で送る働きが弱くなり、便秘やお腹の張りが起こりやすくなる状態のことです。加齢、運動不足、薬の副作用、病気など様々な原因がありますが、脳の機能停止(脳死)とは関係はありません。
5 瞳孔散大・対光反射消失
科目別過去問|4.こころとからだのしくみ
どんな問題もんだいが出でる?
利用者りようしゃを理解りかいする上うえで大切たいせつなからだのしくみ、病気びょうきやその原因げんい...


.png)
-1.png)